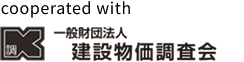COLUMN

BIM/CIMの違いは? CIM導入のメリット5つやデメリット2つも併せて解説
建設業界において業務の効率化や生産性向上の需要が高まる中、注目を集めているのが「建設DX」です。このDX化を推進する上で、多くの人が耳にするようになった言葉に「BIM」と「CIM」があります。
しかし、その違いや何ができるのかといった具体的な違いについて、あまり詳しくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、BIMとCIMの違い、CIM導入のメリット・デメリットなどについて詳しくご紹介します。建設DXの導入を検討している方々は、ぜひ参考になさってください。
まとめ
- ・BIM/CIMの違いについて、BIMは建築情報のモデリング手法、CIMは土木・インフラのモデリング手法。
- ・CIM導入におけるメリットは豊富で、生産性の向上や維持管理の効率化などが挙げられる。
- ・一方で専用ツールが必要であるがために専門の人材が必要であったり、費用がかかったりといったデメリットもある。
BIM/CIMの違い
BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)とCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)は、建築・土木分野における品質向上と生産性向上を目指した取り組みです。
具体的には、建築や構造物の形状、構造などを3次元モデルとして表現し、計画、設計、施工、そして維持管理の各段階において関係者間で共有することを指します。
この3次元モデルを基に、各段階での情報を一元的に管理し、段階的にBIM/CIMモデルを構築していくのです。
上述のように、BIMとCIMはプロセスの進行において3次元モデルを構築し、情報を共有するという点で共通していますが、それぞれが扱う分野や情報の範囲に違いがあります。
以下から詳しく確認していきましょう。
分野の違い
BIMとCIMの利用分野は、主に「建築領域」と「土木・インフラ領域」に分類されます。
BIMは主に建物や施設の設計・建設・運用管理に活用され、建築業界で広く使用されています。
一方、CIMは道路、橋梁、水道、電力などの土木やインフラ整備分野で活用され、公共事業やインフラプロジェクトの設計・建設・管理に役立っているのです。
活用現場の違い
BIMは、規模の大きい建築物や施設の設計や建設に活用されます。例えば、高層ビルや大規模な商業施設、また民間の病院などが挙げられるでしょう。
一方CIMは、複雑な地形や環境条件を考慮する必要がある土木、インフラ整備のプロジェクトなどで活用され、これには道路や橋梁、トンネル、水道施設などが含まれます。
以下からは、主にCIMに焦点を当てて話題を深掘りしていきます。
BIMとCIMはどのようにして注目されるようになったのか
BIMの概念は主にアメリカで生まれ、欧米では一般的に普及しています。
これはアメリカ国内で公共工事の発注者である政府や自治体が、積極的にBIMの導入を推進しているからです。
欧米の後に続くように、日本では2010年頃に国土交通省によってBIMの活用が提唱され、現在ではゼネコンなどの建設業界でも採用が進んでいます。
BIMが建築分野で注目される中、土木分野において同様の概念が必要とされ、それに応じて2012年に国土交通省によってCIMが提唱されました。
2018年5月、国土交通省は建築と土木分野のそれぞれの情報モデリング手法を統一するため、「BIM/CIM」という総称を導入したのです。
国土交通省による推進内容
国土交通省によるBIM/CIMの普及や定着、効果の把握、そしてルールの策定への積極的な取り組みには以下のような背景や目的があります。
国交省がBIM/CIMを推進する背景
BIM/CIMの導入を目指すに至った社会的背景としては、以下の要因が挙げられます。
- 建設産業の活性化(建設業の生産性低下や労働力の高齢化)
- 建設業の国際競争力の向上の必要性
- 社会資本の適切な維持管理の必要性
目的
各段階の測量・調査、設計、施工、維持管理・更新において、建設生産・管理システム全体の効率化・高度化を実現することを目指しています。
この目標を達成するために、BIM/CIMモデルを連携・発展させ、関係者間での情報共有を容易にするための取り組みが行われているのです。
国土交通省は令和5年度より直轄土木業務・工事において3次元モデルの作成・活用を義務化、いわゆる「BIM/CIM原則適用」を定めました。
原則適用で対象とする業務・工事は
・土木設計業務共通仕様書に基づき実施する設計及び計画業務
・土木工事共通仕様書に基づく土木工事(河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事)
・上記に関連する測量業務及び地質・土質調査業務
とされています。
原則適用の対象としない範囲は
・単独の機械設備工事・電気通信設備工事、維持工事
・災害復旧工事
が該当します。
CIM導入のメリット

ここからは、主に土木分野において使われるCIMに焦点を当てて解説していきます。
まずはCIM導入で得られるメリットですが、これには複数あります。
DXの推進において不可欠な知識なので、以下より詳しく解説します。
生産性が向上する
CIMの導入では、建設業界における生産性向上が期待されています。
その具体的な方法として、3次元データを活用した生産方式によるフロントローディングや、コンカレントエンジニアリングなどが挙げられます。
フロントローディングとは?
フロントローディングとは、プロジェクトの初期段階において設計や施工などの作業を前倒しで進め、問題の早期発見と改善を促す手法です。このアプローチにより、後々の仕様変更や手戻りを防ぎ、品質向上と工期短縮が期待できます。
CIMを活用することで従来のような模型を作成する手間が省ける上、効果的な改善策を提案することが可能になりました。
コンカレントエンジニアリング
コンカレントエンジニアリングとは、製造業や建設業などで複数の工程を同時進行させ、関連部門間でリアルタイムな情報共有を行いながら開発プロセスを進める手法です。このアプローチにより、開発期間の短縮やコストの削減が実現されます。
完成形を可視化できる
CIMにより、建築物や構造物の設計から完成までの手順、また周辺環境で発生する問題などが、具体的に可視化されます。従来の2次元図面では理解しづらかった部分も、関係者が共通の認識を持つことが可能になるのです。
このような3次元の視覚化手法を利用することで、施主へのプレゼンテーションや住民説明会など、専門的な知識がない方でも建設プロジェクトを具体的に理解しやすくなります。
情報共有が迅速になる
CIMが活用される主な土木工事は、鉄道や高速道路などの行政区域のインフラ整備に関連しています。これらのプロジェクトでは、関係機関や関係者の数が多く、建築現場よりも複雑な構造が特徴です。
3次元モデル化により関係者間でのイメージの統一が容易になり、情報の不整合が減少する上、地域住民や外部の関係者とのコミュニケーションも円滑になるでしょう。
またCIMを活用することで、積算の作業効率が向上し、正確な数量算出が可能になります。設計から施工までのさまざまな情報を共有することで、プロジェクト全体の効率化が図れるのです。
維持管理が効率化する
CIMでは、収集された測量データなどを統合的に管理・共有・活用することができます。
建設物のモデルを直感的に検索でき、完成後も維持管理の段階で必要な情報を即座に取り出して活用できます。
CIM導入のデメリット
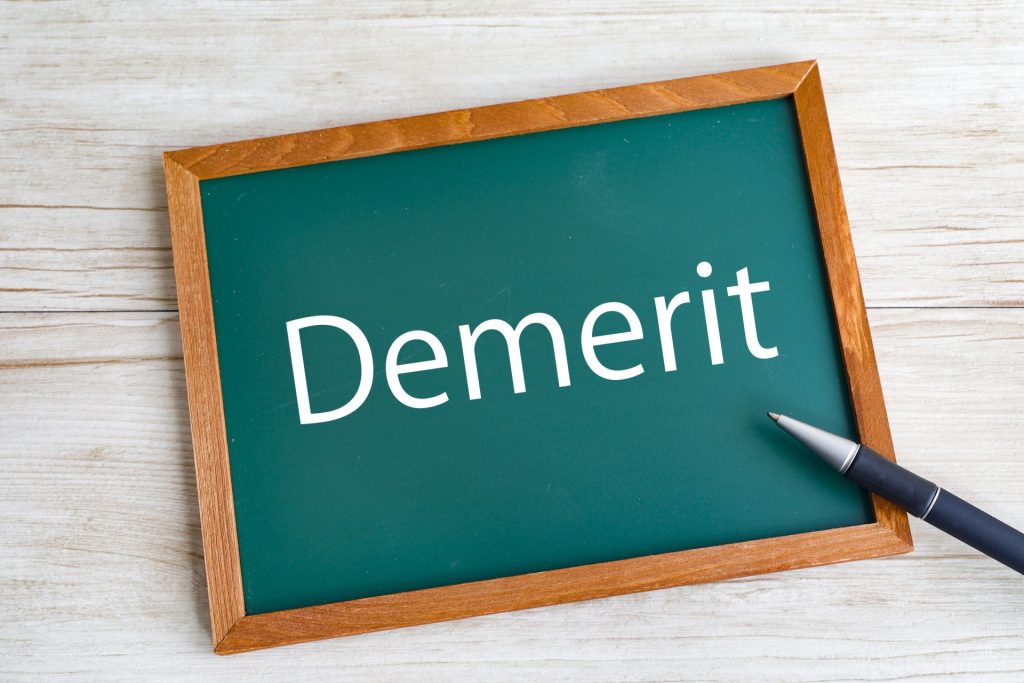
メリットが多いCIMですが、デメリットが一つも無いわけではありません。
デメリットもよく理解した上で導入するようにしましょう。
技術者が必要
CIMのモデリングは、専用のツールを使用し、属性情報を取り込んでいく必要があります。そのため、システムを操作できるスキルを持つ人材が不可欠です。
建設および土木業界では人手不足が慢性化しており、日々の業務に追われながら新たな技術を習得するには時間がかかります。
さらに、システムの導入には追加の業務が発生し、CADなどの既存のシステムからの移行やデータ形式の変換などが必要です。
CIMの今後の普及にはこのよう課題への人材育成が必要不可欠とされています。
費用がかかる
専用ツールの導入や情報端末の整備、属性情報の取得ソフトやシステムの構築には、相応の費用がかかります。また、ツール導入後の運用や維持管理にもランニングコストがかかるのが一般的。
CIMの利点の一つである工事完了後の維持管理には、長期にわたって費用がかかることがある点は頭の隅に留めておくべきでしょう。
【段階別】CIMによって得られる効果
次に、CIMによって得られる効果を建設の段階別に確認していきましょう。
メリットと重複する部分もありますが、CIMのベネフィットをより深く理解できるはずです。
設計段階で得られる効果
設計段階におけるCIMの活用は、地元への説明や関係者との協議、数量の算出、設計の照査など、さまざまな場面で役立ちます。特に設計の照査において、CIMモデルの活用は効率化と品質向上に貢献するはずです。
従来の2次元図面では、鉄筋配置の干渉照査には多大な時間が必要でした。しかしCIMモデルを使用することで、複雑な鉄筋の干渉箇所を視覚的に確認できるため、干渉の検出が容易になりました。
その結果、照査作業の効率化と設計の品質向上が期待されます。
またCIMモデルを利用することで、支障物件との取り合いも簡素化されます。
従来は設計段階で支障物件の確認が難しかったため、作業の手戻りや支障物件所有者との協議に時間がかかっていました。
しかしCIMモデルを用いることで、設計段階で支障物件を確認できるため、作業の効率化と協議の迅速化が期待されます。
施工段階で得られる効果
施工段階におけるCIMの活用は、関係者との協議や住民への説明、安全教育や安全管理、そして設計変更などの場面で重要です。
従来の2次元図面を使用した協議では施工手順の理解が難しく、合意形成に時間がかかることがありました。
しかしCIMモデルを用いることで、施工手順が3次元で視覚的に表現されるため、関係者間での理解が深まり、合意形成が迅速に進むでしょう。
さらに、設計変更に伴う数量算出にもCIMモデルを活用することで効率化が期待されます。CIMモデルにリアルタイムで現場のデータを反映させることで、数量算出を迅速かつ正確に行うことができるため、工事出来高の把握や報告資料作成時間の短縮化が実現し、さらに設計変更に伴う修正ミスを防ぐことができます。
維持管理段階で得られる効果
維持管理の段階では、点検作業における点検箇所の特定や必要な資料の参照、補修方針の検討などにCIMが有効です。
構造物を点検する際には、CIMモデルを使用して重要な点検箇所を容易に把握できます。このモデルには損傷箇所や補修履歴などの情報が組み込まれており、直感的に点検すべき箇所を特定することができるため、点検作業の効率が向上するはずです。
さらにCIMモデルを活用することで、維持管理に必要な情報を迅速に入手できます。
従来は台帳や竣工図面、点検記録などの資料が異なる形式で管理されていましたが、CIMではこれらの情報が一元管理されています。必要な資料をすぐに参照できるため、補修作業の遅れを防ぐことができるのです。
まとめ
本記事で焦点を当てたCIMや、建築情報モデリングであるBIMは、設計段階から3次元モデルを活用し、関係者間での情報共有を促進する新しいアプローチです。
以前は、建築分野におけるBIMと土木分野におけるCIMという区別がありましたが、現在では国際的な標準に従い、統一的に「BIM/CIM」と呼ばれるようになっています。
BIM/CIMの導入により、生産性向上に伴う働き方の改革や、関係者間の迅速な意思決定、管理維持の効率化などが見込まれています。
また、ペーパーレス化やICTの活用による人手不要な施工、工期の短縮化などが実現されることで、労働時間が短縮されるだけでなく、危険な作業からも解放されるでしょう。
DXを取り入れた一歩先の企業になるためにも、BIM/CIMの導入を前向きに検討してみてください。