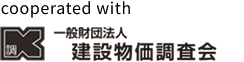COLUMN

カーボンネガティブコンクリートとは?特徴や取り組み企業の事例
世界中でCO2排出量削減が叫ばれる中、建設業界でも脱炭素化の動きが加速しています。従来のコンクリートは製造過程で大量のCO2を排出するため、環境負荷が高いことが課題でした。
こうした背景から、CO2を吸収することで実質的な排出量をマイナスにする「カーボンネガティブコンクリート」が登場し、大きな期待を集めています。これは、地球温暖化の解決に貢献する革新的な技術として注目されています。
まとめ
- ・カーボンネガティブコンクリートとは、製造過程だけでなく、その後の利用段階においても大気中のCO2を吸収・固定することで実質的にCO2排出量をゼロ以下に実現するコンクリートのこと
- ・カーボンネガティブコンクリートの特徴は、CO2を排出しにくい製造方法をとられており、加えてCO2を吸収させる材料、固定化する技術など様々な面で排出量を削減できることにある
- ・実際に日本国内でも高速道路橋脚などでカーボンネガティブコンクリートを利用する建設プロジェクトは存在しており、今後もさらなる開発や利用に期待がかかっている
目次
カーボンネガティブコンクリートとは?

カーボンネガティブコンクリートとは、製造過程だけでなく、その後の利用段階においても大気中のCO2を吸収・固定することで、ライフサイクル全体で実質的にCO2排出量をゼロ以下に実現するコンクリートのことです。
従来のコンクリートとの違い
従来のコンクリートは、その主原料であるセメントの製造過程で大量の二酸化炭素(セメント100kgに対して、CO2が100kg)を排出するため、環境負荷が高い材料とされてきました。 しかし、カーボンネガティブコンクリートは、後述する様々な技術革新により、二酸化炭素の排出量を大幅に削減し、さらには大気中の二酸化炭素を吸収・固定することによって、地球温暖化対策に貢献できる材料として注目されています。
カーボンネガティブコンクリートの特徴
先述したとおり、カーボンネガティブコンクリートは、製造過程だけでなく、そのライフサイクル全体を通じてCO2を吸収・固定することで、大気中のCO2削減に貢献できる点が最大の特徴です。これらの特徴を実現した具体的な技術は以下の通りです。
CO2吸収材料の利用
コンクリートにCO2を吸収する性質を持つ材料を混ぜることで、CO2排出量を削減します。例えば、セメントの一部に特殊な混和材(炭化したバイオマスやγC2Sなど※水酸化カルシウムと珪石を原料とする粉末状の物質)を混ぜて、炭酸化させることによりCO2を吸収するコンクリートが実現されます。
CO2固定技術
コンクリート中にCO2を化学的に固定する技術を利用して、CO2が長期間にわたって固定化されることが期待されます。本技術により、CO2の排出量を実質的に削減できます。
製造の仕組み改善
コンクリートの製造過程におけるセメントを先述した炭化したバイオマスやγC2S、その他産業副産物に混和させることで吸収や固定化する前段階で、CO2排出量自体を削減します。
CO2回収・利用技術
セメント製造過程から排出されるCO2を効率的に回収し、セメント製造に再利用できるエネルギーなどへ変換させます。これにより、CO2を資源として活用し、製造に循環のサイクルが誕生してさらに排出量を減らすことが出来ます
カーボンネガティブコンクリートのメリット
カーボンネガティブコンクリートは、環境面だけでなく、長寿命化においてもメリットをもたらします。
長寿命化
長寿命化については、製造方法や材料の配合によって、従来のコンクリートと同等以上の性能を実現することが可能です。例えば、先述したγC2Sを混ぜ合わせ、大量のCO2をコンクリートに吸収させることにより、炭酸化されることでコンクリートは科学的に安定した状態になり長寿命化が実現できます。炭酸化に目を付けたきっかけは、約5000年前に建てられた大地湾遺跡の住居跡御調査で原型を保っていたコンクリートの製造方法や状態のヒントを経て開発をされています。(通常のコンクリートの寿命は100年ほど)
しかし、一部の技術では、まだ長期的な長寿命化に関するデータが不足しているため、今後の研究開発が期待されています。
環境面

まず、製造過程におけるCO2排出量を大幅に削減できます。従来のコンクリート製造では、セメント製造時に大量のCO2が排出されていましたが、カーボンネガティブコンクリートでは、CO2吸収型セメントを使用したり、製造プロセスを工夫することで排出量を抑制できるからです。
さらに、資源循環を促進する効果も期待できます。建設廃材を再利用したり、副産物を有効活用することで、新たな資源の採取を抑制し、循環型社会の実現に貢献します。
日本の事例紹介
カーボンネガティブコンクリートの開発・普及において、日本の建設業界も積極的に取り組んでいます。ここでは、その先進的な事例をいくつかご紹介します。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合機構(NEDO)
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、政府が設立したグリーンイノベーション基金は2020年に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)として創設され、革新的カーボンネガティブコンクリートの材料・施工技術及び品質評価技術の開発を目指し活動している団体です。
事業概要は、建設活動を通じたカーボンニュートラル社会実現の貢献に向けたコンクリートのCO2排出削減・固定量最大化とコスト低減の両立に向けた技術開発や、大手ゼネコンやセメント混和材メーカー等の関係機関と連携して国内外で幅広い社会実装を目指すというものです。
NEDOが目指す革新的カーボンネガティブコンクリートの開発は、研究開発項目1-①である「セメント低減型コンクリート技術」に「CO2固定型コンクリート技術」、「CCU材料活用型コンクリート技術」を組み合わせる材料開発と、研究開発項目1-②の「大型プレキャスト構造物への適用技術」、「現場打設コンクリートへの適用技術」による施工方法・利用技術を組み合わせた開発を行っています。
さらに研究開発項目2としてCO2排出削減・固定量(環境価値)の見える化、万博などでの実証、技術基準化に向けたデータ収集によってCO2固定量評価と品質管理モニタリングシステムの技術開発も行っています。
鹿島建設「CO2-SUICOM®」
鹿島建設は、CO2を吸収するコンクリート「CO2-SUICOM®」を開発し、注目を集めています。これは、セメントの一部にCO2を吸収する特殊な材料を使用することで、製造過程でCO2を吸収できるという特徴があります。従来のコンクリートと比べてCO2排出量を大幅に削減できるだけでなく、長寿命にも優れていることが確認できます。すでに高速道路橋脚など建設プロジェクトに導入されており、その実用化が進められています。
清水建設「バイオ炭コンクリート」
清水建設は、バイオマスを原料とした炭素材料「バイオ炭」を活用した「バイオ炭コンクリート」の開発に取り組んでいます。これは、セメントの一部にバイオ炭を混ぜることで、従来のコンクリートと同等の性能を維持しながら、CO2排出量を削減する技術です。バイオ炭は、植物などを燃焼させて炭化させた際に得られる炭素物質で、製造過程でCO2を吸収するため、カーボンネガティブな素材として注目されています。実用化に向けて、強度や耐久性などの性能評価や、コスト削減のための製造技術の開発を進めています。
海外の事例と動向
カーボンネガティブコンクリートの開発・普及は、世界中で活発に行われています。特に欧米では、環境意識の高まりを背景に、政府や企業による積極的な取り組みが見られます。
CarbonCure社(カナダ)
カナダのCarbonCure社では、コンクリート製造時にCO2を注入し、コンクリートを固定化する技術を開発し、世界中のコンクリート工場に技術を提供し、すでに数百万トンのCO2を削減しています。
Solidia社(アメリカ)
セメント製造時のCO2排出量を削減し、さらにコンクリート硬化時にCO2を吸収する技術を開発しています。従来のコンクリートよりも強度が高く、耐久性にも優れているとされています。
カーボンネガティブコンクリートの課題と今後の展望
カーボンネガティブコンクリートは、地球温暖化対策として大きな期待が寄せられていますが、実用化に向けてはいくつかの課題も残されています。
まず、従来のコンクリートに比べて製造コストが高いことが挙げられます。新しい技術や材料の導入にはどうしても費用がかかってしまうため、コスト削減は普及に向けて重要な課題です。また、CO2吸収量や強度などに関する明確な評価基準や、関連する法規制の整備も必要です。さらに、カーボンネガティブコンクリートの認知度を向上させ、そのメリットを広く理解してもらうことも重要です。
これらの課題を解決し、技術開発や普及が進むことで、カーボンネガティブコンクリートは、建設業界のCO2排出量削減に大きく貢献することが期待されています。ひいては、カーボンニュートラル実現への貢献、持続可能な社会構築に欠かせない材料となる可能性を秘めています。