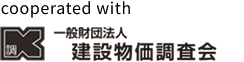COLUMN

CPDの単位を取得する方法3つ! 取得によるメリットも併せて解説
CPDは、技術士、建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士などの職業的なスキルや知識を向上させるために必要な継続的な学習のことを指します。
この制度は、スキルアップを目指す技術者や、人材育成に関心のある企業にとって非常に有益なものです。
本記事では、CPDの概要に触れた後、CPDの単位を取得する方法や単位取得によるメリットを詳しく解説します。
最後までお読みになって、ぜひ参考になさってください。
まとめ
- ・CPDの単位を取得する方法はセミナーの受講・自己学習・研修会などへの参加の3つがあり、自分に合った方法を選択できる。
- ・CPDの単位を取得することは、企業の持ち点に加えられることや、自主のキャリアアップに繋がるなど、企業側・個人、双方にメリットがある。
- ・CPDの単位は換算が必須であり、団体ごとに取得できる単位数が異なる。
CPDの重要性や昨今の動向など、CPDについてより詳しく知りたい方はこちらも併せてお読みください。
▶CPD制度とは? CPD取得のメリット4つ! 費用・登録方法なども解説
CPDの単位を取得する方法

CPDの単位を取得する方法には、主に以下の3つのものがあります。
各々について、詳しく解説します。
セミナー・講座の受講
セミナーや講座に参加すると、内容に応じた単位が取得可能です。団体の審査を経てCPDプログラムとして認定されたセミナーや講座が対象となります。
多くの場合、登録している制度のウェブサイトに認定されたプログラムの一覧が掲載されているので、そこから探すと確実でしょう。
申請先の制度、開催日、開催場所、分野など、さまざまな条件で検索できます。講習受講料が別途必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
教材を使った自主学習
単位取得には、教材を使用した自主学習も含まれます。講習会やセミナーの開催頻度が低く、参加が難しい場合や、仕事が忙しくて時間が取れない方に適しています。
CPDプログラムとして認定された動画の視聴や、専門書や学会誌の購読が対象となりますが、認定されたプログラムで自主学習を行う場合は申請が必要なため、登録している団体のルールを確認してください。
学習後に、CPDシステムにログインし、雑誌に掲載された設問に回答するなど、単位取得のための条件が課せられている場合もあります。
研修会の講師や委員会活動への参加
単位取得の方法には、情報提供型に分類されるものがあります。研修会や講習会の講師、委員会活動への参加、論文の執筆、研究開発への参加などが該当します。
内容に応じて取得できる単位が異なるため、注意が必要です。
CPDの単位を取得することによるメリット
CPDの単位を取得することには、大きなメリットがあります。
企業側、個人、双方にメリットがあるため、各々以下で詳しく解説します。
企業側のメリット
建設会社や設備会社などの企業が工事を請け負う際、入札(総合評価落札方式)が行われることがあります。公共工事を受注するためには、企業の持ち点が重要であり、その中でCPD単位の取得は重要な要素です。
なぜなら、企業の持ち点には技術士、建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士などの有資格者の人数に加え、CPD単位も加点されるからです。これにより技術力の評価が行われるため、入札の結果に大きく影響を与えることになります。
企業の持ち点が上がることで公共工事の受注率が高まり、結果として会社の利益につながるため、CPDの取得には大きなメリットがあるでしょう。
個人のメリット
資格を取得して現場で働き始めると、学習の機会が減ることが多い……と感じる方もいるはずです。そのため、知らず知らずのうちに持っている知識が古くなってしまうことがあります。
しかし、CPDを活用することで、最新の情報や技術、工法について学ぶ機会が増え、常に新しい知識を身につけることができるのです。
さらに他社の技術者と交流する機会も増え、視野が広がることで、自分のキャリアアップにも繋がるでしょう。CPDは企業にとっても重要な制度ですが、個人にも多くのメリットを提供してくれるのです。
建設業者が受けなければいけない経営事項審査とCPD取得の関係性は?

<CPD単位取得と経営事項審査の関係性>
CPDの取得は、公共工事で発注者から直接請け負う建設業者が必須で受ける「経営審査事項」でも大きな役割を果たします。
「経営事項審査」とは、公共工事を受注するために建設業者が必ず受けなければいけない審査のことです。
公共工事の発注者は、入札に参加する建設業者の資格を審査し、客観的な基準と主観的な要素を評価して順位付けを行います。
経営事項審査はそのうちの一部であり、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、および社会的な側面などを評価し、数値化されたデータを用いて評価を行うのです。
特に、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が指定した経営状況分析機関によって実施されます。
令和3年4月の経審改正では、技術者及び技能者の継続的な教育を評価する項目が新設されており、技術者をCPDで評価、技能者点を建設キャリアアップシステムのレベルアップで評価する仕組みが設けられています。
経営事項審査ではCPD単位の換算が必須
たとえ同じ講習を受けたとしても、団体Aと団体Bでは取得できる単位が異なることが普通です。
この相違を調整するため、経営事項審査の際には取得したCPD単位そのものではなく、以下の数値を計算して使用します。
(取得単位数)÷(下表満点30点換算)× 30 = 換算後の取得単位数
例えば、以下の表一番目の公益社団法人空気調和・衛生工学会の換算係数は50なので、この団体で4単位取得した場合は、2.4が換算後の取得単位数になります。
| CPD単位を付与している団体 | 満点30 点換算 |
| 公益社団法人空気調和・衛生工学会 | 50 |
| 一般財団法人建設業振興基金 | 12 |
| 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 | 50 |
| 一般社団法人交通工学研究会 | 50 |
| 公益社団法人地盤工学会 | 50 |
| 公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター | 20 |
| 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 | 50 |
| 一般社団法人全国測量設計業協会連合会 | 20 |
| 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 | 20 |
| 一般社団法人全日本建設技術協会 | 25 |
| 土質・地質技術者生涯学習協議会 | 50 |
| 公益社団法人土木学会 | 50 |
| 一般社団法人日本環境アセスメント協会 | 50 |
| 公益社団法人日本技術士会 | 50 |
| 公益社団法人日本建築士会連合会 | 12 |
| 公益社団法人日本造園学会 | 50 |
| 公益社団法人日本都市計画学会 | 50 |
| 公益社団法人農業農村工学会 | 50 |
| 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 12 |
| 公益社団法人日本建築家協会 | 12 |
| 一般社団法人日本建設業連合会 | 12 |
| 一般社団法人日本建築学会 | 12 |
| 一般社団法人建築設備技術者協会 | 12 |
| 一般社団法人電気設備学会 | 12 |
| 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 | 12 |
| 公益財団法人建築技術教育普及センター | 12 |
| 一般社団法人日本建築構造技術者協会 | 12 |
出典:株式会社建設業経営情報分析センター.「告示別表第18」.
https://www.ciac.jp/keisin/hyotenw/tisiki/cpd ,(参照 2024-05-25).
1人あたりの保有単位の上限
経営事項審査では、各技術者のCPD単位の上限を30と定めています。
この数値は、先述の計算式に基づいて換算された結果です。
いつ取得した単位が有効?
審査基準日前一年間に認定された単位数で判断されます。
毎年この加点を得るためには、継続的学習(CPD)が不可欠なのです。
まとめ
現代のビジネス環境において、職業能力の維持と向上は極めて重要です。
CPDは、この目標を達成するために不可欠な仕組みであり、積極的な取り組みは、職業能力の向上に直結します。
CPDは個人のスキルアップに貢献するだけでなく、企業側にも多くのメリットをもたらすことを認識しておくと、企業への貢献のモチベーションにつながるかもしれません。
ぜひ、CPDに積極的に取り組み、自身の技術や自身が所属する企業の発展を実現させましょう。