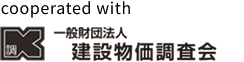COLUMN

CPD制度とは? CPD取得のメリット4つ! 費用・登録方法なども解説
CPDとは、建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士などの職業上のスキルや知識を向上させるための制度です。
この制度は、スキルアップを望む技術者や、人材育成に課題を抱える事業者にとって非常に有益と言えます。
本記事では、CPDの概要や、CPD取得のメリット、そしてCPD登録方法などについて詳しく解説します。
CPDは職業能力を向上させるための貴重な機会であるため、ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
まとめ
- ・CPDとは建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士などの能力の「見える化」を可能にする制度であり、事業者・個人ともに欠かせないもの。
- ・CPDは技術者が所属する事業者・技術者個人ともにメリットが豊富にあり、持ち点に影響したり自身の能力を客観視したりする上で重要な要素。
- ・CPDの登録方法は4ステップ。企業が資格取得などをサポートする環境を整備している場合、積極的に登録を推奨。
CPD制度とは?
CPD(Continuing Professional Development)とは、建築や土木関連など、資格を持つ技術者を対象にした継続教育制度です。この制度では、有資格者がセミナーや講習を受講することで「CPD単位」が与えられます。セミナー、講習会などのプログラムの受講により、「継続的なスキル向上」「CPD単位による能力の見える化」が実現し、自己研鑽が促されるだけでなく、客観的な評価も可能にするのです。
一部の資格では更新制度がないため、継続した自己研鑽が必要ない資格も存在します。その点、CPDは積極的に自己研鑽を行っている技術者とそうでない技術者とを区別できる制度とも言えるでしょう。現在、多くの行政機関が建設工事の入札などでCPD単位を加点し、評価の対象にしているため、CPD単位を取得することは自身が所属する企業のためにも、自身のためにもメリットの大きいことです。
CPDの重要性・必要性について
技術系の資格を持つ方にとって、CPDは非常に重要な制度です。なぜなら、技術や業界の動向が常に変化しているため、自身の知識やスキルを最新の状態に保つ必要があるからです。
建築士や建築施工技師、土木施工管理技士などの専門家は、新しい技術や規制の変更に迅速に対応し、プロフェッショナルとしての能力を維持・向上させる必要があります。
CPDプログラムに参加することで、最新の情報にアクセスし、業界内のベストプラクティスを学び、自己成長を促進することができるでしょう。
また、CPDは単なる知識の更新だけでなく、専門家同士の交流やネットワーキングの場でもあります。プログラムに参加することで、他の専門家とのつながりを築き、新たなビジネス機会やキャリアの可能性を探ることもできます。
結果として、CPDは個々の専門家にとってキャリアの発展や業界への貢献に不可欠な要素となるのです。
CPDとCPDSの違いとは?
CPDに加えて、CPDS(Continuing Professional Development System)という類似した概念が存在することをご存じでしょうか。
CPDとCPDSの主な違いは、それぞれの運営団体にあります。
CPDは建設系CPD協議会によって運営されていますが、CPDSは一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会(以下、全国技士会)が運営しています。
全国技士会は、全国の土木施工管理技士会や橋梁建設、塗装、現場技術に特化した技士会など、合計50の技士会から構成される連合体です。
全国技士会は建設系CPD協議会に加盟しているため、他の加盟団体の登録者でも、全国技士会のセミナーや講習を受講した際に加盟団体のユニット登録申請が可能となっています。
CPDとCPDSの内容に大きな違いはありませんが、CPDSは主に土木施工管理技士の専門知識や技術力、倫理観の向上を目的とした教育システムと覚えておくと良いでしょう。
CPDとCPDSの違いについては、以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
建設系CPD協議会
CPDを運営する建設系CPD協議会として、以下のような団体が存在します。
- 公益社団法人 土木学会
- 公益社団法人 日本建築士会連合会
- 公益社団法人 技術士会
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
- 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会
- 一般社団法人 全日本建設技術協会
- 一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
- 一般財団法人 建設業振興基金
- 一般財団法人 交通工学研究会
上記の組織に限らず、多くの団体が建設系CPD協議会に加盟しています。
建設系CPD協議会は、建設業界における技術者の能力維持やスキルアップを支援するために、関連する学会や協会と連携し、継続教育の推進に取り組んでいます。
CPD制度の昨今の動向
近年のCPDの進展の中でも特筆すべき動きは、対象資格の拡大です。
(一財)建設業振興基金は建設系CPD協議会に加盟しており、2018年4月から「電気工事施工管理技士」「管工事施工管理技士」をCPD制度の対象として追加しています。
これにより、建築・設備施工管理CPD制度が開始されました。
これまで、電気工事施工管理技士や管工事施工管理技士を対象としたCPD制度は存在せず、業界ではその拡大が望まれていましたが、2018年4月以降、土木・建築・電気工事・管工事の施工管理に関わる技術者が、CPD制度を活用できるようになったのです。
この拡大により、業界内の多くの技術者が専門知識と技術力を向上させ、技術者の地位向上に寄与しています。
【事業者】CPD取得のメリット

建設会社や設備会社などが公共工事の入札に参加する際、企業が成功するためには持ち点が極めて重要です。この持ち点には、CPD単位の取得が大きく影響します。
企業の持ち点は、技術士や建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士などの有資格者の数だけでなく、CPD単位も考慮されます。CPD取得者の増加は、企業の技術力向上につながり、公共工事の入札成功率向上に貢献するのです。
したがって、企業は積極的にCPD単位を取得し、技術力の向上を図ることが重要です。CPD取得は企業にとって戦略的な投資であり、競争力を高めるための重要な手段となります。
【個人】CPD取得のメリット
CPDを取得することには、個人にも大きなメリットをもたらします。
主なメリットは、以下の3つです。
スキルアップが見込める
個人のスキルアップを促進するためには、施工5大管理に関する最新情報や技術を学ぶ機会が重要です。工程管理、品質管理、安全管理、原価管理、環境管理などの領域での知識や技術を継続的に更新することは、建設業界での競争力を維持する上で必要不可欠でしょう。
特に中小企業や零細企業では、企業内の研修体制が整っていないことが多く、従業員が最新の情報や技術にアクセスする機会が限られています。このような状況下で、CPD制度は有効な学習の場として活用される可能性があります。
また、経営者側は社内教育の重要性を認識してはいるものの、人材不足や教育体制の整備が難しい場合があります。このような状況でCPD制度を活用することは、企業の技術力向上や人材育成に貢献する良い手段と言えるでしょう。
他社との違いを客観的に把握できる
日々の業務において、自社の手法やアプローチに精通していることは重要ですが、他社の手法やアプローチを知る機会は一般的には限られています。
CPD制度を活用することで、他社の技術者との交流が可能となり、異なる視点やアプローチを学ぶことができます。
これにより、他社の技術レベルや取り組み方を把握するだけでなく、自社や自身の位置付けを客観的に評価することができるようになるでしょう。
この交流によって、自社や自身の技術レベルに関する新たな気付きを得ることもあります。自身の技術レベルを相対的に把握することは、今後の成長やキャリアの方向性を見つける上で重要な要素となります。
キャリアアップに役立つ
建設業界では、人手不足や高齢化といった課題が深刻化しており、特に若手技術者の専門技術継承が難しい状況があります。このような状況下で、中小企業や零細企業における将来の不安が高まっています。
CPD制度を活用することで、建設業界におけるキャリア形成の可能性を探ることができるでしょう。CPDを通じて、将来のキャリアパスや業界の動向を把握し、自身のキャリアに対する具体的な計画を立てることができます。
このような取り組みは、将来のキャリア設計や業界での成長に役立ちます。CPD制度は、個々の技術者が自己成長を促進し、業界全体の発展に貢献するための有効な手段と言えるでしょう。
CPDの登録方法

CPD制度への登録手続きは以下のステップで行います。
- 制度の選択: 利用するCPD制度を選択します。
- 資格の確認: 制度に必要な資格や条件を確認します。
- 費用の確認: 利用料金や登録料などについて確認します。
- 登録手続き: 制度のホームページや申込書などを通じて登録手続きを行います。
CPD単位を取得するためには、事前に選んだ制度に登録して個人IDを取得する必要があります。セミナーや講習を受講する前に、まずは制度への登録を済ませておきましょう。
制度の選択
CPD制度を提供している団体は複数存在しますので、まずは利用する団体の制度を選択しましょう。
団体は「建設系CPD協議会」の項目でご紹介したようなものが存在します。
CPD登録者数や推奨獲得単位、年間のプログラム数などは、各団体によって異なりますので、詳細はそれぞれの団体の公式ホームページでご確認ください。
資格の確認
各団体が求める対象者の資格は異なるため、事前に確認することが重要です。
例えば、(一財)建設業振興基金では、「施工管理を行う技術者であれば、資格の有無は問われません」としています。
一方、(公財)建築技術教育普及センターでは、以下の資格を持つ者を対象としています。
- 建築士
- 建築設備士
- 建築施工管理技士(技士補)
- 電気工事施工管理技士(技士補)
- 管工事施工管理技士(技士補)
また、一部の団体では資格以外の条件も設定されているため、詳細は各団体の公式ホームページやガイドラインを確認してください。
費用の確認
各団体によって、制度登録に必要な料金は異なります。
例えば、(一財)建設業振興基金では、新規参加手数料として1,000円の入会金と2,500円の年会費が必要です。2年目以降は年会費のみが必要で、その額は2,500円です。
一方、(公財)建築技術教育普及センターでは、年会費が3,300円であり、(一社)建設コンサルタンツ協会では会員の種別に応じて会員登録料や年会費が無料となる場合があります。
また、実績証明書やカードの発行には別途料金が必要な場合もあるため、詳細は各団体の規定を確認することが重要です。
登録手続き
制度の選択が完了し、資格や条件に問題がなければ、次は実際に登録手続きを進めましょう。
多くの団体では、オンラインでの登録が可能ですので、自宅やオフィスから手続きを行うことができます。
登録に際しては、保有する資格の詳細や登録番号などの情報を入力する必要がある場合がありますので、事前に準備しておくことがスムーズな手続きを行うコツです。
CPD制度に登録したあとは、セミナーや講座の受講などによって単位を取得します。
CPDの単位取得については、以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
▶CPDの単位を取得する方法3つ! 取得によるメリットも併せて解説
建築家資格制度とCPD単位取得の関係
建築家資格制度規則では、登録建築家には建築の設計や監理に関する知識の継続的な習得が求められています。そして登録を維持するためには、定められたCPD単位を更新の際に取得する必要があるのです。この要件を満たさない場合、登録が失効してしまうことになります。
まとめ
CPD制度は今日のビジネス環境において、職業能力を磨くために欠かせない要素です。
職業能力の向上を目指すなら、CPD制度に積極的に取り組むことが不可欠です。
個人や企業にとって、CPD制度は重要なメリットをもたらしますし、その重要性は今後ますます高まるでしょう。
セミナーや講義以外にも、様々な方法でCPD単位を取得できるため、ホームページなどで詳細をチェックしてみてください。
企業が資格取得などをサポートする環境を整備している場合、さらなる選択肢が開けるかもしれません。
ぜひ、CPD制度に積極的に参加して、キャリアアップを実現してください。