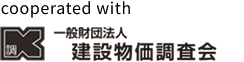COLUMN

ICT施工の問題点とは? 現状の課題と解決事例を解説
現在、建設業界ではICT施工が積極的に推進されています。
国や業界団体の支援を受けてICT施工の普及が進んでおり、建設業界ではこれによって得られる大きなメリットに期待が寄せられています。
しかし、一般的にはそのメリットに焦点が当てられがちですが、課題が存在しているのも事実です。
本記事では、そもそもICT施工とは何なのかに触れた後、ICT施工の課題とその解決事例などについて詳しく解説します。
最後までお読みになって、ぜひ参考になさってください。
まとめ
- ・ICT施工とは、情報通信技術を活用して測量・設計・施工などのプロセスを効率的に行おうという取り組み。
- ・ICT施工には設備投資に費用がかかったり、人材確保が難しかったりする課題が多くある。
- ・しかし、それらの課題は建機やソフトウェアメーカーとの緊密な連携や、国や業界団体が主催する講習に参加することで解決する場合もある。
目次
ICT施工とは?
ICT施工とは、建設工事における「情報通信技術(ICT)の総合的な活用」を指し、国土交通省が推進するi-Construction(アイコンストラクション)の3大施策の一つとして位置づけられています。
コンピュータやインターネットを用いた情報の取り扱い技術であり、これによって人々の生活を豊かにする技術として注目を集めています。
具体的には、測量、設計、施工、施工管理、納品といった建設工事の各プロセスにおいて、ICTを積極的に活用して効率化することがICT施工の目的です。
ICT施工の課題

ここまでの内容だけを読むと、ICT施工はデメリットがないように思えるかもしれません。
しかし、ICT施工には課題が複数あるのです。
具体的にどのような課題があるのかを確認してみましょう。
設備投資に費用がかかる
施工業者にとってICT施工の最大の課題は、設備投資にかかる費用です。
ICT施工を実現するためには、新しい測量機器、ソフトウェア、建設機械を導入する必要があり、これらは従来の機器よりも高額です。ハードウェアをレンタルすることも可能ですが、その費用も従来機器と比較すると高くなっています。
加えて、採算が取れるかどうかは実際に工事が完了するまで分かりません。
1つの工事にかかる人件費や時間の削減や、ICT施工の導入により受注が増える可能性など、先行投資と考えることもできますが、この初期費用の大きさがネックとなり、導入を躊躇する企業が多いのが現状です。
通信環境に依存する
ICT施工の導入に際して考慮すべき課題として、工事の進捗が現場の通信環境に依存する点が挙げられます。
ICT施工では、ドローンやICT建設機械、Webカメラ、現場間コミュニケーションツールなど、さまざまなツールが電波を利用して情報をやり取りします。
しかしながら、工事が山間部やトンネル、超高層ビルなどの電波の届きにくい場所で行われる場合、通信の安定性が懸念されるのです。このような状況では、ICT施工の実施が困難になることがあります。
また、通信の不安定さが精度に影響を与え、作業の効率性を低下させる可能性もあり得るでしょう。
現在では、こうした課題に対処するために、現場での無線通信環境の強化や、位置情報を正確に取得するための技術開発が進んでいます。ICT施工を円滑に実施するためには、これらの技術的な課題解決が重要です。
人材確保が難しい
ICT施工の導入に際し、建機やソフトウェアを扱う人材の確保は重要な課題です。
ICT施工に必要な建機については、従来の建設機械とは異なりますが、新たに人材を確保する必要はありません。国や建機メーカーが提供する講習に参加すれば、従業員は必要な技術や知識を効果的に習得できます。
特に、MC(マシンコントロール)建機を使用することで、自動制御による高精度な施工が可能となり、従業員のスキル向上にも貢献するでしょう。
測量に使用するレーザースキャナについても、専門の講習を受けることで、迅速かつ正確に操作できるようになります。
一方、3次元設計データの作成にはソフトウェアの熟練が必要です。
新しいソフトウェアの導入に際しては、ソフトウェアメーカーのサポートを受けながら、シミュレーションやトライアルを行い、問題を事前に克服することが重要です。
外部委託による測量や設計データの作成も考慮されますが、内部での対応を強化することでコストを節約できます。
国や地方自治体、ソフトウェアメーカーが主催する研修やトレーニングに積極的に参加することで、社員のスキルアップを図り、効果的なICT施工の実現が可能になります。
ICT施工の導入に伴う研修や技能向上にかかる費用は、助成制度を活用することで軽減できる場合があります。
ICT施工の課題にある背景
ICT施工に関する「課題」がしばしば指摘される背景には、バブル崩壊後の建設業界の構造変化が影響しています。
約20年前、建設業従業員がピークに達した直後にバブルが崩壊し、土木・建設工事の受注数は低迷を続け、人手が余る状況が長く続きました。
その結果、人件費を安く抑えることができ、建設現場では設備投資を控え、人的な技能や人数に頼る運用が一般的となりました。機械設備を導入するよりも、多くの人を雇用する方がコストを抑えられたのです。
しかし、平成の終わり頃には状況が変わりました。景気の回復やオリンピック開催に伴う需要増加、相次ぐ災害復旧などにより、土木・建設業界は深刻な人手不足に直面しています。
現在、ICT施工について言及される課題の多くは、バブル崩壊後の人手が余っていた時期の発想に基づいています。
とはいえ、現在の人手不足の状況では、安価で高技能な人手を集めることは困難です。そのため、設備投資を行い、熟練者が少なくても対応できる「システム」を整備する必要があります。
さらに、通信環境の不便さや代替機の不足、システムダウンなどの問題も、導入促進開始当時の10数年前と比べて、行政や民間事業者のサポート体制が大幅に改善されました。想定されるトラブルについても、事前に関係者と相談すれば解決できることがほとんどです。
課題の多いICT施工は導入しない方が良い?
万が一の事態への懸念や、職人の重要な技能がICT技術に取って代わられることへの抵抗感を持つ方もいらっしゃるでしょう。
しかし、建設業界におけるICT施工への移行は避けられません。国が建設業へのICT技術導入を「i-Construction」普及事業として支援している以上、現場へのICT技術の普及は広がるでしょう。
これは、かつて人力で行っていた排土作業がブルドーザーに置き換えられた時代の変化と同様です。手作業での排土やブルドーザーの故障時の手動バックアップ技術も貴重ですが、ブルドーザーの効率性には勝てません。
同様に、今後はブルドーザーや油圧ショベルの操作技能よりも、ICT建機の操作や3次元設計データの作成、3次元出来形管理などの技能が必要になることが増えるでしょう。
従来の建設現場の視点からは、ICT施工には課題も多く存在します。しかし、昨今の社会の変化スピードをみるとICT施工を積極的に取り入れる会社とそうでない会社で差がつくと考えられます。
ICT施工の課題は解決できるものも多い

ICT施工の導入には、多くの課題がありますが、ほとんどは克服可能なものです。国は平成20年代初頭から建設業界でのICT活用を推進し、導入事例を基に課題や要望を洗い出し、制度や基準を改善してきました。
「i-Construction」に基づく支援制度も、初期から比べると建設業者にとって扱いやすくなっていますが、それでも導入過程ではトラブルや実務上の課題に直面することがあります。また、政府の政策動向を把握することも情報収集の負担となるでしょう。
これらの課題に対処するためには、建機やソフトウェアメーカーとの緊密な連携が不可欠です。技術的な問題や行政対応に関するヒントを得るために、情報交換や相談を積極的に行うことが重要です。この記事でも述べたように、問題解決に向けた示唆を得ることができます。
さらに、国や業界団体、民間企業が主催する講習に積極的に参加することも推奨されます。最新の動向や現場の実情を把握し、他の参加者との交流を通じて知識を深めることができます。
ICT活用における課題と解決事例
ICT活用における課題と、それをどう解決したのかを、実際の事例で確認してみましょう。
事例:道路土工
施工数量は「暫定切土:28,710m3、暫定盛土:20,910m3 」。
主な工種は道路土工です。
起工測量の場面での課題は、高低差が大きく海風が強いことでした。
これに対してTLSによる 起工測量を自社にて実施したところ、社内に3次元設計データ作成のノウハウを 蓄積することが可能になりました。
また、「人員手配が難しいため、作業員を削減し、施工を実施したい」という課題がありましたが、ICT適用範囲外にもICTを適用たところ、荒整形されている状態での法面整形に活用するのであれば、従来の倍程度の施工能力を発揮することが可能という結果が得られました。
※参考:国土交通省.「ICT活用における課題と対応事例」.
https://www.mlit.go.jp/common/001299661.pdf ,(参照 2024-06-20).
事例:道路改良(掘削工)
施工数量は「延長170m、掘削工28,664m³」。
主な工種は道路改良(掘削工)です。
設計段階での課題は、「暫定形状のため、予算に応じて平場の仕上がり標高が変更されるが、修正を最小限にしたい」というものでした。
ちなみに法面部は設計が確定しており、平場部は標高未確定の状態です。
そこで法面と平場部を分けて3次元データを作成したところ、設計変更時の負担が軽減し、結果的に施工日数を36日も縮減することに成功しました。
※参考:国土交通省.「ICT活用における課題と対応事例」.
https://www.mlit.go.jp/common/001299661.pdf ,(参照 2024-06-20).
まとめ
先述の通り、ICT施工に関する課題は将来的に解決される見通しです。
社会の変化と共に、これらの課題も徐々に「当たり前」の一部として認識されることでしょう。
ただし、変化の過程では設備投資の資金調達や、関係者の技術・知識の浸透不足によるトラブルが頻発する可能性があります。これらの細かなデメリットを克服するためには、行政担当者や同業他社、取引先企業との継続的な情報交換が不可欠です。
業界内での情報交換の場や民間企業の講習を通じて、関係者がICT施工に対する対応状況やトラブル発生時のバックアップ体制、経費計上のルールなどについて情報を収集し、スムーズなICT施工の導入を進めていくことが重要でしょう。