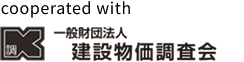COLUMN

舗装工事とは?役割や工事の種類、5つの施工手順について解説
日本で初めて道路舗装が行われたのは、東京に自動車が登場した明治36年ごろのことです。大正8年には、旧道路法や旧道路構造令などの法令がつくられ、アスファルト舗装を中心とした道づくりが本格的に始まりました。
道路の舗装工事はなぜ必要なのでしょうか。この記事では、舗装工事の役割や、舗装に使われる主な材料、施工の流れについて分かりやすく解説します。
まとめ
- ・舗装工事とは道路の表面をアスファルトやコンクリートなどを敷き詰めて保護する工事のこと
- ・舗装工事の役割は、ぬかるみや粉塵の発生を防止し、安全性や快適性を向上させることなどが挙げられる
- ・舗装工事の種類はアスファルト舗装・コンクリート舗装・特殊舗装の3つに分けられる
舗装工事とは?

舗装工事とは、道路の表面にアスファルトやコンクリート、砂利、石などを敷き固め、耐久性を高める工事です。簡易舗装を含めた道路の舗装率は、令和2年の時点で約82.5%(うち、一般国道は99.5%)に達しています。
国土交通省は、舗装工事のガイドラインとして「舗装の構造に関する技術基準」を定めています。国や地方自治体などの道路管理者は、舗装の性能指標や浸透水量などの基準を守り、工事計画を策定しなければなりません。
| 舗装の性能指標 | 疲労破壊輪数 | 輪荷重(一つの車輪にかかる重さ)を繰り返し加えた際に、ひび割れが生じる回数 |
|---|---|---|
| 塑性変形輪数 | 輪荷重を繰り返し加えた際に、わだち掘れが生じる回数 | |
| 平たん性 | 路面の高低差を測定したときの凹凸の少なさ | |
| 浸透水量 | 舗装の路面下に浸透する水の量 | |
舗装はさまざまな材料を何層にも積み重ねてできている
道路の舗装は目に見える部分だけでなく、さまざまな材料を何層にも積み重ねてできています。一般的な道路は、表層・基層・路盤(ろばん)・路床(ろしょう)の4つの層で構成されており、舗装工事では一番下の路床から順に施工します。
各層に使われる材料や、厚さの目安は以下の表のとおりです。
| 材料 | 厚さの目安 | ||
|---|---|---|---|
| 表層 | 密粒度アスファルト混合物(注)など | 5cm | |
| 基層 | 粗粒度アスファルト混合物など | 5cm | |
| 路盤 | 上層路盤 | 粒度調整砕石など | 20cm |
| 下層路盤 | 切込砕石、切込砂利など | 30cm | |
| 路床 | 地盤(関東ローム層など) | – | |
注:アスファルト混合物とは、砂利と砂を混ぜ合わせ、アスファルトを熱して加えたものを指します。
舗装工事の3つの役割

舗装工事の役割は、大きく分けて3つあります。
・道路の泥濘化や粉塵の発生を防止する
・走行時の安全性・快適性が向上する
・良好な道路景観や沿道環境を創出する
道路の泥濘化や粉塵の発生を防止する
舗装工事には、道路の泥濘化や粉塵の発生を未然に防ぐ役割があります。
砂利道など、未舗装の状態の道路は、季節や天候の変化によって路面状態が著しく悪化するのが特徴です。例えば、雨が多い季節は土が水分を含んでやわらかくなり、路面がぬかるむ「泥濘化」という現象が発生します。特に黒色土や関東ローム層など、含水比が高い土壌で発生しやすい現象です。
一方、空気が乾燥する季節は、地表の水分が失われ、土砂が粉塵となって舞い上がるケースもあります。道路の泥濘化や粉塵による被害を防止するためにも、舗装工事は欠かせません。
走行時の安全性・快適性が向上する
舗装工事を実施することで、走行時の安全性・快適性が大きく向上します。未舗装の道路では、自動車が走行すると路面にわだちができ、後続車両が運転しにくくなるため、舗装された道路を走るときよりゆっくり運転しなければなりません。
また路面状態が悪いと、タイヤのすり減りも大きくなり、車両が故障するリスクも高まります。平らな道路よりも運転に時間がかかるため、ガソリン代が高くなるのもデメリットです。
ドライバーの目線で見ると、舗装された道路には、快適性や安全性の面で多くのメリットがあります。
| 舗装された道路 | 未舗装の道路 | |
|---|---|---|
| 運転 | 速い・安全 | ゆっくり・危険 |
| 騒音 | 小さい | 大きい |
| 車両 | 壊れにくい | 壊れやすい |
| タイヤ | すり減りにくい | すり減りやすい |
| ガソリン代 | 安い | 高い |
良好な道路景観や沿道環境を創出する
周辺の環境や街並みと調和した舗装材を使用することで、道路の景観性を高められます。特に歩道では、顔料を添加したカラー舗装材などを用いることで、個性的な空間演出が可能です。
例えば、東京都は平成2年にシンボルロード整備事業を開始し、“美しさや潤いのある道路づくり”に取り組んできました。令和3年度には、新たに「東京ストリートヒューマン1st事業」が始まり、日比谷通りや明治通りなどの景観整備が予定されています。
舗装工事は3種類ある
舗装工事の種類は、アスファルト舗装・コンクリート舗装・特殊舗装の3つに分けられます。
日本の道路行政では、東京・大阪などの大都市を中心として、アスファルト舗装による道づくりを推進してきました。近年は舗装技術の発達により、排水性舗装や透水性舗装、保水性舗装などの特殊舗装を採用するケースが増えています。
特に高速道路では、雨天時の走行安定性が高い排水性舗装が広く普及しています。舗装工事の主な種類や、それぞれの特徴を知っておきましょう。
| 舗装工事の種類 | 特徴 | |
|---|---|---|
| アスファルト舗装 | 表層にアスファルト混合物を使用した舗装 | |
| コンクリート舗装 | 表層にセメントコンクリート版を使用した舗装 | |
| 特殊舗装 | 排水性舗装 | 上部に透水層、直下に不透水層を使用した舗装 |
| 透水性舗装 | 全体が透水層となった舗装 | |
| 保水性舗装 | 舗装の隙間に保水材を使用した舗装 | |
コストが安価なアスファルト舗装

アスファルト舗装は、表層にアスファルト混合物などの材料を使用した舗装方法です。日本では、明治11年に完成した東京神田昌平橋において、初めてアスファルト舗装が取り入れられました。
| 素材 | アスファルト 骨材(砂利や砂など) |
|---|---|
| 性質 | すぐに固まるため工期が短い 気温や路面温度に影響されやすい |
| 用途 | 一般的な道路に広く用いられる |
アスファルト舗装には、他の舗装方法と比べコストが安価で、工事期間が短いというメリットがあります。一方、気温や路面温度に影響されやすく、耐熱性が低いのがデメリットです。暑い季節は路面温度が高温になるため、ヒートアイランド現象の原因ともいわれています。
耐久性に優れるコンクリート舗装

コンクリート舗装は、表層にセメントコンクリート版などの材料を使用した舗装方法です。主に大型車両の交通量が多く、路面が傷みやすい場所に用いられます。
| 素材 | セメント 水 骨材(砂利や砂など) |
|---|---|
| 性質 | 固まるまでに時間がかかる 磨耗に強く、わだちができにくい |
| 用途 | 大型車両の交通量が多く、傷みやすい場所 路面の補修が困難な場所(トンネルなど) |
コンクリート舗装のメリットは、摩耗に強く、耐久性が高いという点です。一方、セメントが固まるまで時間を要するため、アスファルト舗装よりも工期は長くなる傾向にあります。
新たな技術が使われた特殊舗装
特殊舗装は、従来型の舗装の問題点を克服するため、特殊な素材や構造を用いた舗装方法です。特にアスファルト舗装の一種である排水性舗装・透水性舗装・保水性舗装の3つが知られています。
国土交通省によると、それぞれの舗装方法の違いは以下のとおりです。
| 構造 | 性質 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 排水性舗装 | 上部に透水層、直下に不透水層を設置する | 雨水は透水層を通り抜け、側溝へ流れ出る | 走行安全性の向上 騒音の低減 |
| 透水性舗装 | 全体を透水層とする | 雨水を地中に還元する | 水循環環境の保全(街路樹育成) 雨水の流出を抑制 |
| 保水性舗装 | 舗装の隙間に水を吸着する材料(保水材)を詰め、雨水をためる | 気温が上がったときに水分が蒸発する | 気化熱により、路面の温度を下げる ヒートアイランド現象の緩和 |
その他、歩道や交通量が少ない道路(公園など)では、景観性を考慮したカラー舗装や、レンガや天然石などを用いたブロック系舗装を採用するケースもあります。
舗装工事の施工手順を5つのステップで解説
舗装工事では、あらかじめ現場の測量調査を行ってから、路床・路盤・基層・表層の順に施工していきます。舗装工事の大まかな流れを5つのステップで解説します。
1.測量・調査
2.路床工事
3.路盤工事
4.基層工事
5.表層工事
測量・調査
舗装工事が始まる前に、まずは現場の測量・調査を行います。
| 測量 | 現場の状況を確認し、設計図と相違点がないか比較する |
|---|---|
| 調査 | 障害物となるもの(埋設管など)や、周辺地域への影響がないか調査する |
発注者からもらった設計図と比較し、認識の齟齬がないかを確認するのが目的です。また地中に埋設管などの障害物がないか、周辺地域への影響はないかなどを調査し、施工の基本方針を決定します。
路床工事
舗装工事は、道路の最下層にある路床部分の工事から始まります。路床は自然にできた原地盤(関東ローム層など)であることが多く、主に土でできているのが特徴です。
地盤改良が必要な場合は、ブルドーザーやモーターグレーダーなどの重機を用いて土を均してから、ロードローラーで締め固めます。路床工事を行うことで、地盤の支持力が高まり、上層から伝わる交通荷重をしっかりと支えられます。
路盤工事
路盤とは、路床の上にある砂利や砕石でできた層です。上層路盤と下層路盤に分かれています。
それぞれ材料(路盤材)が異なり、上層路盤には粒の大きさを揃えた粒度調整砕石、下層路盤にはふるい分けを行っていない切込砕石・切込砂利を用います。路床工事と同様に、モーターグレーダーなどの重機で整地してから、ロードローラーで締め固めるのが施工の流れです。
粒度の異なる砂利や砕石が、クッションのように衝撃を受け止めることで、交通荷重を支える仕組みです。
基層工事
路盤工事が完了したら、基層工事を行います。
基層は上層路盤の上にある、厚さ5cmほどのアスファルト混合物でできた層です。基層工事では、アスファルトフィニッシャーという重機を用いて、工事現場に運ばれてきたアスファルト混合物を加熱し、路面に敷き均します。
表層部分と比べ、比較的粒度が粗いアスファルト混合物(粗粒度アスファルトコンクリート)を用います。
表層工事
表層工事は、舗装工事の最後の工程です。アスファルトフィニッシャーを用いて、密粒度アスファルトコンクリートを舗装し、表面をロードローラーでしっかり締め固めます。
基層工事と異なり、表層は利用者が直接目にする部分であるため、美しい仕上がりが求められます。アスファルトの温度が十分に下がったら、路面に車線の区画線(中央線や境界線など)を描き、工事は完了です。
舗装工事の役割や舗装の材料ごとの違いを知ろう
舗装工事には、道路の表面を平らにし、耐久性を高めるという役割があります。路面をアスファルトやコンクリートなどの材料で覆うことで、季節や天候に関係なく、快適に走行することが可能です。
近年は舗装技術の発達により、降雨時の排水性を改善した特殊舗装も普及しつつあります。特に高速道路では、雨天時の走行安定性の高さを重視し、排水性舗装を用いることが一般的です。