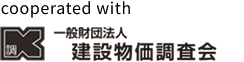COLUMN

道路工事の安全対策とは?実際の事故事例と事故防止に必要な対策について
道路工事は、道路を新しく舗装したり、傷んだ部分を整備したりする工事です。都心部では、周辺の交通事情に配慮し、夜間に工事が行われることが一般的です。
しかし、車や歩行者が通行する中で道路工事を実施するケースも多く、しっかりと安全対策を講じる必要があります。安全対策が不十分な場合、通行人や現場の作業員の死亡事故につながるかもしれません。
この記事では、道路工事における実際の事故事例や、事故防止に必要な対策を紹介します。
まとめ
- ・道路工事の安全対策として、工事現場の手前に予告看板を設置したり、進入を防止するバリケードを設置するなど状況に応じていくつか挙げられる
- ・道路工事における事故は平成27年以降、減少傾向にある一方で、安全対策が不十分な状態での死亡事故などもまだまだ発生している
道路工事の安全対策とは?

道路工事の安全対策とは、工事中の安全を確保し、事故を未然に防止するための対策です。他の建設工事における安全対策と異なり、現場の作業員だけでなく、道路上を通行する車や歩行者の安全も考慮する必要があります。
国土交通省が定める「土木工事安全施工技術指針」によると、工事が始まる前に以下の事項を調査し、安全対策を検討することが大切です。
| 交通への影響 | 交通量、通学路、バス路線、地下鉄、地下街への出入口、迂回路など |
|---|---|
| 環境への影響 | 騒音、振動、煙、ごみ・ほこり、学校・病院・商店・住宅に与える影響など |
| 搬入道路 | 幅員、路面の強度、舗装の有無、交通量、交通規制など |
| 資機材の置場 | 外部および現場よりの搬入出路の交通量、置場の管理など |
道路工事を含む工事事故の発生件数は、平成27年以降、減少傾向にあるものの、以前として死亡事故も起きています。例えば、平成29年6月8日には、道路維持工事の高所作業中に作業員が落下し、死亡する事故が発生しました。
道路工事では、現場の作業員の安全が確保されているか、工事中の交通誘導が適切に行われているかなど、しっかりと安全対策を講じることが大切です。東京都のように、道路工事の安全対策に問題がないかを発見するため、夜間パトロールを実施している自治体もあります。
| 道路監察パトロールによる指摘箇所 | 件数(令和3年度) |
|---|---|
| 保安施設での問題 | 53件 |
| 復旧での問題 | 4件 |
| 掘削での問題 | 3件 |
| 路面履工での問題 | 1件 |
| その他 | 35件 |
道路工事における実際の事故事例
道路工事では、現場の作業員が通行車両などと接触し、死亡する事故が発生しています。ここでは、厚生労働省が公表している「労働災害事例集」の中から、実際に起きた事故事例を3つ紹介します。
道路の中央線の塗り替え作業中、3名の作業員がトラックに激突された事例

1つ目は、道路(片側1車線)の中央線の塗り替え作業中に、3名の作業者がトラックにはねられ、うち1名が亡くなった事例です。
| 業種 | 道路建設工事業 | |
|---|---|---|
| 工事の種類 | 道路建設工事 | |
| 事故の類型 | 交通事故(道路) | |
| 被害者数 | 死亡者数 | 1人 |
| 休業者数 | 2人 | |
| 発生要因 | 防護・安全装置がない 作業員の睡眠不足など | |
事故当日は、元請けの現場監督1名、下請けの作業員および交通誘導員5名の計6名で道路工事を行っていました。道路使用許可条件では、「片側交互通行」と「防護車の配置」の2点が必須でしたが、いずれも守られていませんでした。
交通誘導員がすでに西方向から車両を誘導していたところ、東方向からも8tトラックが進入してきたため、反対側の交通誘導員が通行させました。トラックは作業区間に進入すると、突然センターラインを越え、塗り替え作業中の作業員3名に激突しました。
この事故が起きた原因として、以下の2点が考えられます。
・道路使用許可条件を遵守しておらず、上り下り車線ともに車両を通行させており、防護車も配置していなかった
・元請けの現場監督が下請けの作業員に対し、安全な作業を行うための具体的な指示を与えていなかった
同様の事故の再発を防ぐには、道路使用許可条件を守り、防護車の配置などの安全対策をしっかりと行う必要があります。また工事を開始する前に、安全な作業を実施するための手順を定め、作業員に周知徹底しておくことも大切です。
照明灯の取り付け作業中、高所作業車が大型トラックに激突された事例
2つ目は、照明灯の取り付け作業中に、道路を走行していた大型トラックが高所作業車と接触し、1名の作業員が亡くなった事例です。
| 業種 | 電気通信工事業 | |
|---|---|---|
| 工事の種類 | 電気通信工事 | |
| 事故の類型 | 交通事故(道路) | |
| 被害者数 | 死亡者数 | 1人 |
| 休業者数 | 0人 | |
| 発生要因 | 区画、表示の欠陥 危険感覚の欠如など | |
事故当日は、高所作業車を道路脇の空き地に停車させ、国道沿いのポールに照明灯を取り付ける作業を行っていました。交通整理は事業主が担当しており、作業場所への進入を禁止するため、路面にカラーコーンを設置していたことが確認されています。
取り付け作業の前に周辺の木の枝の剪定を行っていたところ、10tトラックがスピードを緩めることなく進入し、高所作業車に激突しました。高所作業車の上で作業をしていた作業員と、運転を担当していた現場監督(無資格者)が道路上に投げ出され、作業員は頭蓋骨を骨折し死亡しました。
この事故が起きた原因として、以下の5点が考えられます。
- 通行車両の進入を防ぐため、カラーコーンしか設置していなかった
- トラック運転手が判断を誤り、作業場所に進入してきた
- 通行車両に対する誘導方法が適切でなかった
- 高所作業車の運転を無資格者に行わせていた
- 高所作業車のバケットの位置が低く、車両が不安定になっていた
同様の事故の再発を防ぐには、通行車両の進入を防ぐ柵などを作業場所に設けることや、通行車両への誘導方法を見直し、専任の交通誘導員を配置するといった対策が挙げられます。
交通整理の作業中、警備員がバックしてきたトラックに轢かれた事例
3つ目は、工事現場で交通整理を行っていた警備員が、バックしてきた4tトラックに轢かれ、亡くなった事例です。
| 業種 | 道路建設工事業 | |
|---|---|---|
| 工事の種類 | 道路建設工事 | |
| 事故の類型 | 交通事故(道路) | |
| 被害者数 | 死亡者数 | 1人 |
| 休業者数 | 0人 | |
| 発生要因 | 作業環境の欠陥 合図、確認なしに車を動かすなど | |
事故当日は、2車線道路の片側を10mにわたって閉鎖し、ヒューム管を埋設する工事を行っていました。午後になると、周辺の住民から車を出したいという突発的な申し出があり、車庫の前に覆工板を敷くことになります。
しかし、現場が非常に狭く、トラックの運転手はバック運転を余儀なくされました。運転手は後方確認を行ったものの、交通整理を担当していた警備員がトラックの死角に移動したため、後部車輪に巻き込み死亡させました。
この事故が起きた原因として、以下の3点が考えられます。
・警備員が死角の位置にいたため、運転手から視認できなかった
・狭隘な現場内を一人でバック運転せざるを得ない状況だった
・突発的な作業に対する安全対策が事前に決められていなかった
同様の事故の再発を防ぐには、たとえ突発的に生じた作業であっても、その場でしっかりと話し合い、安全対策を検討する必要があります。また現場内でトラックをバックさせる場合は、必ず誘導者を配置し、バック誘導を行いましょう。
道路工事の事故防止に必要な対策

ここでは、道路工事の事故防止につながる安全対策を4つ紹介します。
・正確で分かりやすい交通誘導を実施する
・工事現場の手前に予告看板を設置する
・進入を防止するバリケードを設置する
・現場内の段差はしっかりと養生する
正確で分かりやすい交通誘導を実施する
道路工事では、作業現場に進入してきた車両により、接触事故が発生しています。工事現場に交通誘導員を配置し、車両を適切に誘導することで事故を防止できます。特に片側交互通行を実施する際は、必ず交通誘導員を配置しましょう。
交通誘導員は、正確かつ分かりやすい交通誘導を心掛けることが大切です。停車・発進・車線変更などの合図がドライバーに正しく伝わらなかった場合、むしろ事故を誘発する可能性があります。
道路工事の現場責任者は、交通誘導員への指導を徹底し、ドライバーに対して適切な方法で交通誘導を行っているか確認しましょう。
工事現場の手前に予告看板を設置する
工事現場の手前の道路上に、工事の予告看板を設置しておくことも大切です。予告看板を見たドライバーが、事前に車線を変更したり、渋滞を回避するために迂回したりすることで、車両との接触事故を予防することが可能です。
予告看板は、ドライバーに見やすく設置する必要があります。例えば、安全対策が徹底された工事現場では、以下のような工夫を行っています。
・看板に記載する文字・数字は、正確に分かりやすく記入する
・夜間でもはっきり見えるようにLEDで表示する
・電柱や街路灯などの遮蔽物と重ならないように設置する
・渋滞している場合は、渋滞の手前にも予告看板を追加する
進入を防止するバリケードを設置する
工事現場に歩行者用の通路を設ける場合は、バリケードを設置することが大切です。歩行者の進入を防止するだけでなく、バリケードとの接触音により、現場の作業員が異常を早期発見できます。
バリケードには、コーンバーや単管バリケード、A型バリケードなどの種類があります。安全性の観点から推奨されているのは、ドライバーからの視認性が高く、接触音が大きいA型バリケードです。
| バリケードの種類 | 特徴 |
|---|---|
| コーンバー | 接触音が小さく、異常に気づきにくい カラーコーンを連結するため、接触した際に一斉に倒れやすい 歩行者が手をついた際に自立せず、転倒の恐れがある |
| 単管バリケード | 通行車両などが衝突した際に、単管パイプがドライバーと接触する危険性がある |
| A型バリケード | 接触音が大きく、作業現場の異常を早期発見できる 反射板がついており、ドライバーからの視認性が高い |
現場内の段差はしっかりと養生する
仮舗装の凹凸や覆工板、マンホールの蓋などの段差は、しっかりと養生しておくことが大切です。段差をそのままにしていると、車両の安全な走行を阻害するだけでなく、騒音や振動の原因にもなります。
バリアフリーの観点からも、高齢者や障害のある方が安全に通行できるような対策が必要です。すり付け勾配が5%以下になるように、ベニヤ板のスロープなどを設置して段差を解消しましょう。
道路工事における事故防止のため、しっかりと安全対策を考えよう
道路工事の現場では、作業員の転落事故や、進入してきた車両との接触事故など、日々さまざまな事故が起きています。作業員が死亡したり、後遺障害を負ったりする事例も多いため、しっかりと安全対策を考えることが大切です。
正確で分かりやすい交通誘導や、工事予告看板の設置など、事故防止につながる安全対策を導入しましょう。