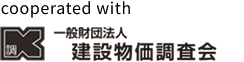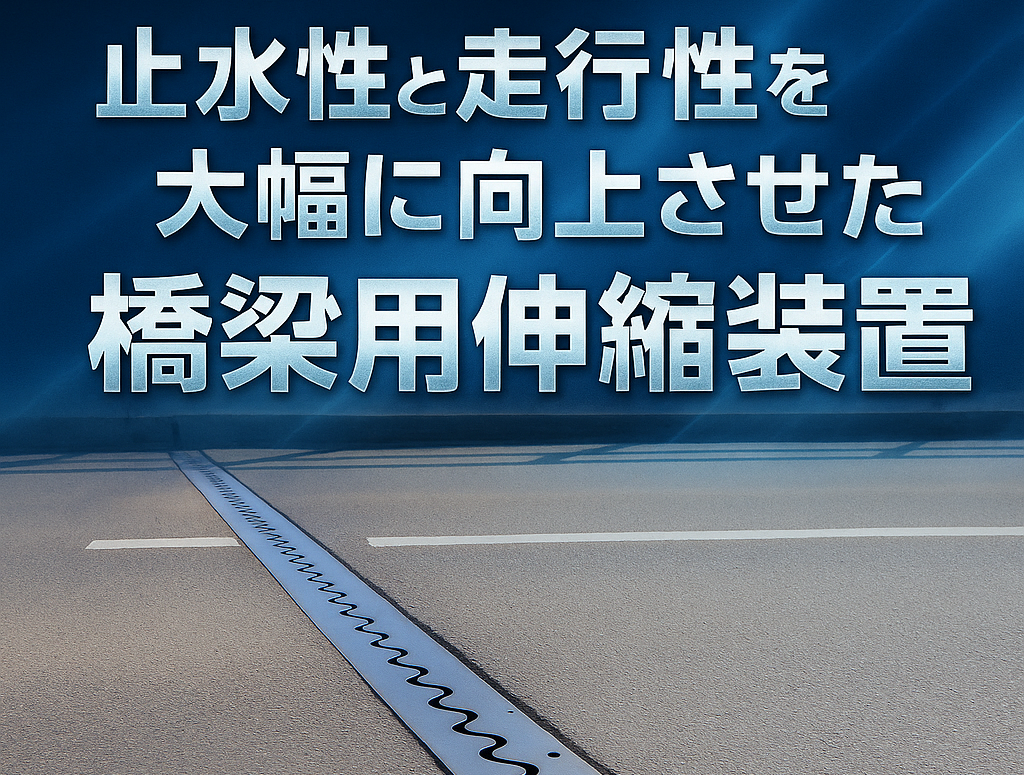COLUMN

アーチ橋とは?構造や仕組み、作り方を詳しく解説!
アーチ橋(きょう)は、古代ローマの水道橋に代表されるように、古くから利用されてきた半円形の橋です。壊れにくく丈夫なことから、長大橋(橋長100メートル以上)の建設に適しています。
この記事では、アーチ橋の構造や、荷重を支える仕組み、作り方について解説します。
まとめ
- ・アーチ橋とは、アーチにより自重や自動車などの荷重を支える構造を用いた橋
- ・丸くカーブしたアーチリブが上方向からかかる力を水平方向に逃がす構造
- ・アーチ橋には、支保工(しほこう)や張り出し架設工法など、さまざまな作り方がある
目次
アーチ橋とは?
アーチ橋とは、拱橋(きょうきょう)とも言い、“アーチにより自重や自動車などの荷重を支える構造を用いた橋”を指します。
半円形のアーチ部材は、アーチリブ(拱肋)という名称でも呼ばれ、石やコンクリート、鉄鋼など、さまざまな材料でできています。丸くカーブしたアーチリブが、上方向からかかる力を水平方向に逃がすことで、橋全体をしっかりと支える仕組みです。
アーチ橋は長大橋の建設に適しており、支間長が50~250メートルの場所で採用されることが一般的です。ただし、アーチの両端に大きな力(水平反力)がかかるため、基礎地盤が強固な場所にしか建設できません。
またアーチ橋は景観性が高く、自然と調和することから、日本を代表する名橋にもアーチ橋が含まれています。例えば、2023年に創建350年を迎えた錦帯橋(きんたいきょう)は、世界的にも珍しい木造のアーチ構造を持つ橋です。

このように力学的な合理性と景観性を兼ね備えたアーチ橋は、古代エジプトやバビロニア、ローマなどで古くから建設され、その一部は現在も残っています。
ちなみに国内では、上記の中央部分の支間長が約380メートルの広島空港大橋が日本最大のアーチ橋です。

日本では江戸時代にアーチ橋の建設が始まる
アーチ橋は、日本でも長い歴史のある橋の一つです。国内でアーチ橋の建設が始まったのは、江戸時代のころと言われています。特に九州地方では、中国やオランダから技術が伝わり、石造のアーチ橋が盛んに建設されました。
例えば、重要文化財に指定された眼鏡橋(長崎県)は、中国から渡来した僧の如定(にょじょう)によって、1634年に建設されたアーチ橋です。長崎市内に現存する12のアーチ橋のうち、唯一の二連アーチ橋でもあります。

また現存する日本最古の石造アーチ橋として、1502年に建設された天女橋(沖縄県)が有名です。

江戸時代のアーチ橋は木造か石造でしたが、明治時代になると鉄の橋(鋼橋)が架けられるようになりました。また明治時代の末には、コンクリート製の橋(コンクリート橋)も登場します。材料工学や技術の進歩により、アーチ橋にも丈夫で長持ちする材料が用いられるようになりました。
アーチ橋にはどんな構造がある?代表的なものを解説
アーチ橋には、さまざまな構造が存在します。ここでは、次の3つの観点から、アーチ橋の代表的な構造形式を紹介します。
| 分類 | 構造形式 | 特徴 |
|---|---|---|
| アーチの支点条件 | 固定アーチ | アーチリブの両端が基礎地盤と一体化し、固定されているもの |
| 2ヒンジアーチ | アーチリブの両端がヒンジ構造になっているもの | |
| 3ヒンジアーチ | アーチリブの両端がヒンジ構造で、中間部にもヒンジ結合点があるもの | |
| アーチと通行路の位置関係 | 下路橋 | 橋の主構造(主桁やトラス、アーチなど)の下方に通行路を設けたもの |
| 中路橋 | 高さ方向で見て、橋の主構造の中間部に通行路を設けたもの | |
| 上路橋 | 橋の主構造の上方に通行路を設けたもの | |
| アーチの部材構成 | ソリッドリブアーチ | アーチ部材にI形鋼や鋼管、箱形断面を用いたもの |
| ブレースドリブアーチ | アーチ部材としてトラスを用いたもの |
アーチの支点条件による分類
アーチ橋では、橋の上部に荷重が加わると、水平方向の力になって両端の支点(支承)に負荷がかかります。この支点部の構造によって、固定アーチ、2ヒンジアーチ、3ヒンジアーチの3つに分類できます。
固定アーチの特徴
固定アーチとは、アーチ橋の支点部が基礎地盤と一体化し、完全に固定された構造を指します。主に長支間(橋台や橋脚の距離が長いもの)のアーチ橋に採用されます。
また石造や鉄筋コンクリートのアーチ橋は、支点部をヒンジ構造にすることが難しいため、固定アーチ橋として建設することが一般的です。
2ヒンジアーチの特徴
2ヒンジアーチとは、アーチ橋の両端が固定されず、一定の範囲で回転するヒンジ構造になっているものを指します。現代の鋼アーチ橋では、2ヒンジアーチを採用することが一般的です。
3ヒンジアーチの特徴
3ヒンジアーチとは、アーチ橋の両端に加えて、頂点にもヒンジが取り付けられたものを指します。地盤沈下などが原因で左右の支点部が動いても、第三のヒンジが働くことにより、無理な力がかかりにくいのがメリットです。
しかし、国内では建設例が少なく、大阪府の銀橋(桜宮橋)のみが3ヒンジアーチを採用しています。
アーチと通行路の位置関係による分類
アーチ橋をはじめとした橋梁は、橋の主構造と通行路の位置関係によって、下路橋(かろきょう)、中路橋(ちゅうろきょう)、上路橋(じょうろきょう)の3種類に分かれます。
アーチ橋の場合、通行路がアーチリブの下部にある橋が下路橋、中間部にある橋が中路橋、上部にある橋が上路橋です。それぞれ以下のような種類があります。
| 分類 | アーチ橋の例 |
|---|---|
| 下路橋 | ランガー橋、ローゼ橋、ニールセンローゼ橋、ブレースドリブタイドアーチ橋、トラスドランガー橋 |
| 中路橋 | リブアーチ橋 |
| 上路橋 | 上路式アーチ橋、逆ローゼ橋、逆ランガー橋、ブレースドリブアーチ橋、スパンドレルブレースドアーチ橋 |
特にローゼ橋、ランガー橋、ニールセン橋(ニールセンローゼ橋)の3つは、アーチ橋においてよく見られる構造形式です。
ローゼ橋(ローゼ桁橋)の特徴
ローゼ橋とは、アーチリブと補剛桁(橋全体の剛性を補うために設ける桁)の両方が太く、曲げモーメントへの抵抗を受け持つ構造形式です。国内では、広島県の巴橋が代表的なローゼ橋の一例です。なお、曲げモーメントとは、構造物や部材を曲げ、変形を生じさせようとする力を指します。
上路橋の中にもローゼ橋と同様の構造のものがあり、逆ローゼ橋と呼ばれます。ローゼ橋よりも両端に強い力が加わるため、強固な基礎地盤が必要です。
ランガー橋(ランガー桁橋)の特徴
ランガー橋とは、曲げモーメントへの抵抗を補剛桁のみが受け持つ構造形式です。アーチリブに曲げ剛性はなく、他のアーチ橋よりも細くなっています。国内のランガー橋の例として、広島県の紅葉橋などが挙げられます。
ニールセン橋(ニールセンローゼ橋)の特徴
ニールセン橋とは、ローゼ橋の一種で、アーチリブから補剛桁にかけて斜めにケーブル(吊り材)を張ったものを指します。ケーブルの部材にはワイヤーロープを用いることが一般的ですが、棒鋼も用いられます。通常のローゼ橋よりも剛性が高く、振動にも強いのが特徴です。
アーチの部材構成による分類
アーチ橋は、アーチリブに使われる部材によって分類することも可能です。主な部材構成には、ソリッドリブアーチとブレースドリブアーチの2種類があります。
ソリッドリブアーチの特徴
ソリッドリブアーチとは、アーチ部材として、I形鋼や鋼管、箱形断面などを用いたものを指します。特にアーチリブが鋼管でできたアーチ橋は、パイプアーチと呼んで区別することがあります。
国内では、大三島橋(愛媛県)がソリッドリブアーチ、宇品橋(広島市)がパイプアーチの代表例です。
ブレースドリブアーチの特徴
ブレースドリブアーチとは、アーチ部材がトラス構造(三角形の集合体)になっているものを指します。ソリッドリブアーチよりも強度が高く、長大橋の建設に用いられることが一般的です。日本国内で最大の支間長を誇る広島空港大橋にも、ブレースドリブアーチが採用されています。
アーチ橋はなぜ安定する?荷重を逃がすアーチ構造の仕組み
アーチ橋の安定性が高いのは、アーチ構造と呼ばれる仕組みによるものです。
アーチ橋に荷重がかかると、鉛直力(上下方向の力)に加えて、弓なりに反ったアーチ部材を押し広げる水平力が発生します。アーチ橋の両端は、動かないようにしっかりと支えられているため、鉛直力や水平力に対して反力(アーチ反力)が働きます。
すると、アーチ橋にかかる力は、アーチ部材の断面に働く圧縮力に変換されるため、簡単には曲がったりたわんだりしません。このようにアーチ構造が上方からの力を圧縮力に変換する原理を「アーチアクション」と呼びます。
アーチ橋の主な作り方・架設方法を紹介
アーチ橋には、支保工(しほこう)や張り出し架設工法など、さまざまな作り方があります。
| 分類 | 架設方法の例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 支保工 | 接地式支保工 | アーチ橋の荷重を支える架台(支保工)を先に作り、その上でアーチリブを組み立てていく古典的な工法 |
| セントル工法 | 山岳地帯のように地形が平坦でなく、接地式支保工を用いることが困難な場所に適した工法 | |
| 張り出し架設工法 | ピロン工法 | ピロン柱と呼ばれる橋脚を先に作り、数メートルずつアーチリブを張り出していく工法 |
| トラス工法 | 張り出し架設工法の中でも、アーチリブや補剛桁などでトラスを形成しながら張り出していく工法 | |
| その他 | ロアリング工法 | アーチリブを2つに分割して製作し、中央部分で閉合する工法 |
アーチ橋の構造や荷重を支える仕組みについて知ろう
アーチ橋は、石やコンクリート、鉄鋼などでできた半円形のアーチ部材を特徴とした橋です。景観性にも優れており、国内で重要文化財に指定されたアーチ橋も多数あります。
アーチ橋が荷重を支える仕組みは、上方からの力を水平方向に逃がすアーチ構造によるものです。アーチ橋の安定性の高さは、古くから知られており、今も古代ローマの水道橋などが現存しています。
アーチ橋は、アーチリブの支点条件や、通行路との位置関係、使用されるアーチ部材などによって、さまざまな分類があります。特にローゼ橋、ランガー橋、ニールセン橋(ニールセンローゼ橋)の3つは、日本各地で見られる代表的な構造形式です。
アーチ橋の代表的な構造や、安定して荷重を支える仕組みについて知っておきましょう。