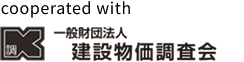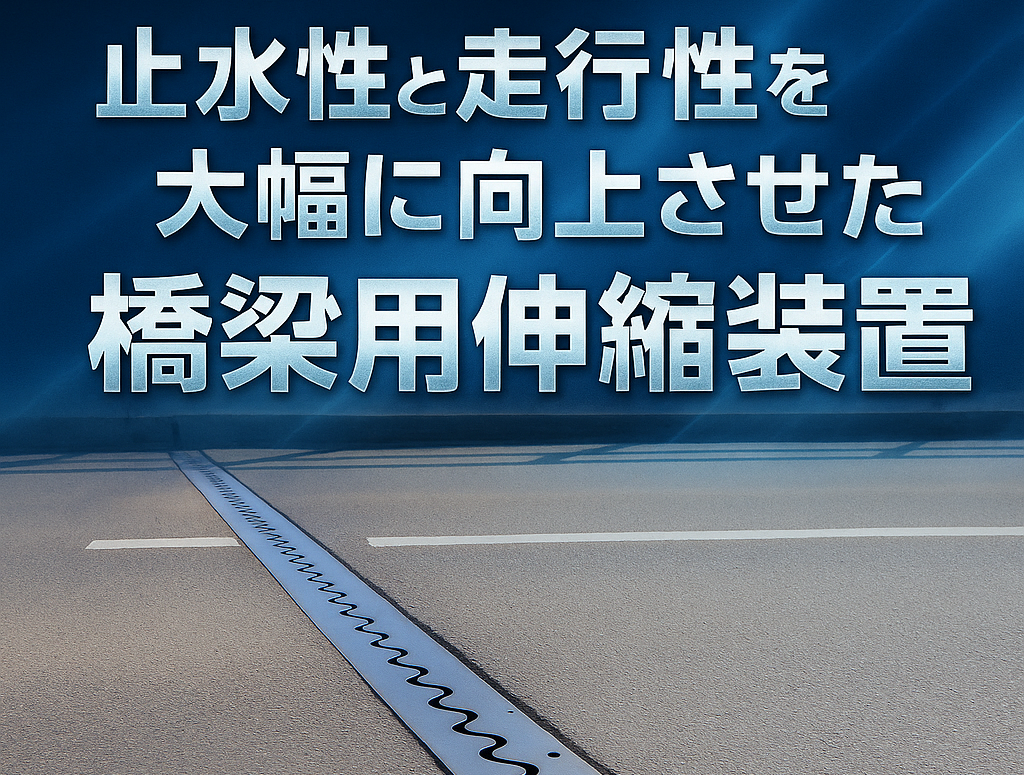COLUMN

アーチ橋の特徴とは?メリット・デメリットを詳しく解説
アーチ橋は、日本でも江戸時代から見られる橋の構造形式です。力学的に安定したアーチ構造を採用しているため、壊れにくく強度が高いという特徴があります。
一方、アーチ橋には横からの力に弱いといった欠点もあります。この記事では、アーチ橋の特徴や、メリット・デメリットについて解説します。
まとめ
- ・アーチ橋は、力学的に安定しており、橋長100メートル以上の長大橋の建設に適した構造形式などメリットが多くある
- ・デメリットとして、両端に強い力がかかるため、強固な基礎地盤が必要になることなど挙げられる(例外もある)
- ・しかし、架設工法を選べば、地形条件が厳しい場所でも架橋できる
アーチ橋とは?3つの特徴を分かりやすく紹介

アーチ橋とは、建物の屋根などに見られる半円形の構造(アーチ構造)を、橋梁の建設にも利用したものです。ゆるやかなカーブを描く部材はアーチリブと呼ばれ、石やコンクリート、鉄鋼などの材料でできています。
アーチリブには橋全体を支える役割があり、中にはアーチリブのみで全ての荷重を受け持つ構造形式も存在します。その他、アーチリブをタイ部材で連結するものや、路面下の桁(補剛桁)によって剛性を補うものなど、設計上の考え方が多様なのもアーチ橋の特徴です。
ここでは、アーチ橋に見られる特徴を3つ紹介します。
・曲がりを付けたアーチ部材で荷重を支える
・石やコンクリート、鉄鋼などの材料が用いられる
・無補剛アーチ橋と補剛アーチ橋の2種類がある
曲がりを付けたアーチ部材で荷重を支える
アーチ橋の特徴は、曲がりを付けたアーチリブと呼ばれる部材を用いて、橋全体の荷重を支える点です。
アーチ橋では、上方からかかる荷重が水平方向に逃され、アーチリブの両端にある支点部(支承部)に伝達される構造になっています。そのため、橋が真っ直ぐ伸びた桁橋(けたばし)などと比べ、曲がったり、たわんだりし辛いという特徴があります。
このアーチ構造の安定性は古くから知られており、古代エジプトやバビロニア、ローマなどで、石造のアーチ橋が多数建設されてきました。今日でも、古代ローマ時代に架けられた水道橋が現存しています。
石やコンクリート、鉄鋼などの材料が用いられる

アーチ橋に用いられるのは、石やコンクリート、鉄鋼などの材料です。使用する材料によって、石造アーチ橋、コンクリートアーチ橋、鋼アーチ橋と呼び名が変わります。
アーチ橋に用いられる材料には、圧縮強度(注)が高いという共通点があります。特にコンクリートは圧縮強度が高く、近代的なアーチ橋ではコンクリートを鉄筋で補強したRC構造(鉄筋コンクリート構造)を採用することが一般的です。
注:圧縮強度とは、“材料が耐えることのできる単位面積当たりの最大圧縮力”を指します。
またアーチリブには、I形鋼や箱形断面、鋼管などの鋼材を用いることも多く、ソリッドリブアーチという名称で呼ばれます。ソリッドリブアーチの中でも、鋼管でできたものはパイプアーチと呼んで区別します。国内では、大三島橋(愛媛県)がソリッドリブアーチ、宇品橋(広島市)がパイプアーチを用いたアーチ橋の代表例です。
無補剛アーチ橋と補剛アーチ橋の2種類がある
アーチ橋の構造形式は、無補剛アーチ橋と補剛アーチ橋の2つに分類できます。
| アーチ橋の分類 | 主な例 |
|---|---|
| 無補剛アーチ橋 | 固定アーチ、2ヒンジアーチ、3ヒンジアーチ、タイドアーチ |
| 補剛アーチ橋 | ランガー橋、ローゼ橋、ニールセン橋(ニールセンローゼ橋) |
無補剛アーチ橋とは、橋全体の荷重をアーチリブのみで支える構造形式を指します。アーチリブの支点部の形状によって、固定アーチや2ヒンジアーチ、3ヒンジアーチなどの種類に分けられます。またアーチリブの両端をタイ部材で連結し、水平反力(地盤がアーチリブを押し戻そうとする力)を軽減するタイドアーチ橋も、無補剛アーチ橋の一種です。
一方、アーチ橋の路面下に補剛桁(注)を設置し、アーチリブと一体となって荷重を支えるものを補剛アーチ橋と呼びます。補剛アーチ橋には、ランガー橋やローゼ橋、ニールセン橋(ニールセンローゼ橋)などの種類があり、それぞれアーチリブや補剛桁の太さが異なります。
注:補剛桁とは、“吊り橋やアーチ橋において、橋全体および橋床部の剛性を補うために設ける桁”のことを指します。
このようにアーチ橋には、さまざまな種類があります。架設地点の地形や周辺の自然環境に合わせて、自由に構造形式を選べるのもアーチ橋の魅力の一つです。
アーチ橋の4つのメリット
ここでは、アーチ橋ならではのメリットを4つ紹介します。
・部材に圧縮力のみが作用するため、力学的に安定している
・橋長100メートル以上の長大橋の建設に適している
・景観性が高く、自然と調和したデザインを実現できる
・架設工法を選べば、地形条件が厳しい場所でも架橋できる
部材に圧縮力のみが作用するため、力学的に安定している
アーチ橋は、力学的な安定性が高い構造形式です。
一般的な橋では、上から荷重がかかったときに曲げモーメント(注)が発生します。曲げモーメントが加わると、橋の上側では圧縮応力(縮む力)、下側では引張応力(伸びる力)が働き、部材がひび割れたり破壊されたりする可能性があります。
注:曲げモーメントとは、“構造物や部材に曲げ変形を生じさせようとする力”を指します。
一方、アーチ橋は上向きのアーチ構造によって橋全体が支えられています。そのため、上から荷重がかかっても、曲げモーメントがほとんど発生しません。
アーチリブの支点部には、部材を押し広げようとする水平方向の力が加わります。しかし、アーチ橋の両端は強固な基礎地盤に支えられているため、反作用として部材を内側に押し戻す圧縮力が働きます。
アーチ橋では、基本的にこの圧縮力のみが作用するため、構成部材の引張強度を考慮する必要がありません。そのため、圧縮強度が高いコンクリートなどの部材を用いることで、壊れにくく丈夫な橋梁を建設できます。
橋長100メートル以上の長大橋の建設に適している
アーチ橋は曲げやたわみに強いことから、長大橋の建設にも適しています。長大橋とは、橋台や橋脚の支間長(しかんちょう)が長く、桁の長さが100メートル以上の橋を指す言葉です。

例えば、上部画像の最大支間長が約380メートルの広島空港大橋(広島県)も、上路式ブレースドリブ固定アーチ橋というアーチ橋の一種です。
景観性が高く、自然と調和したデザインを実現できる
アーチ橋は強度の高さだけでなく、景観性の面でも優れています。美しい弧を描くアーチリブの形状や、自然と調和したデザインによって、古くから人々に愛されてきました。
周辺の自然環境に合わせて、構造形式を選べるのもアーチ橋のメリットです。例えば、アーチリブの下に通行路がある下路橋(かろきょう)は、アーチの部分が単独で安定して見えることから、河川や湖の景観によく合います。
また深い谷地形がある場所では、通行路がアーチリブの上に位置する上路橋(じょうろきょう)や、中間部に位置する中路橋(ちゅうろきょう)を採用することが一般的です。
周辺の自然と一体化した美しさから、眼鏡橋(長崎県)や坂戸橋(長野県)、錦帯橋(山口県)など、多くのアーチ橋が国の重要文化財に指定されています。
架設工法を選べば、地形条件が厳しい場所でも架橋できる
アーチ橋は架設工法を選べば、峡谷や山間部など、地形条件が厳しい場所に建設することもできます。アーチ橋の架設工法は、大きく支保工と張出し架設工法の2種類に分かれます。
| アーチ橋の架設工法 | 特徴 | 主な例 |
|---|---|---|
| 支保工 | アーチ部分の土台となる支保工を組み、その上にアーチリブを作成していく工法 | 接地式支保工、セントル工法 |
| 張出し架設工法 | まず橋脚を設置し、左右に数メートルずつ張り出していく工法 | ピロン工法(ピロン張出し架設工法)、トラス工法(トラス張出し架設工法)、メラン併用工法、仮支柱併用工法 |
このうち、ピロン工法やトラス工法などの張出し架設工法は、通常は橋を建設するのが困難な山岳地帯や、河川を渡る箇所で採用されます。また支保工の一種であるセントル工法も、中小規模のアーチ橋であれば、平坦でない地形で架橋することが可能です。
アーチ橋の2つのデメリット
一方、アーチ橋にはデメリットも2つあります。
・両端に強い力がかかるため、強固な基礎地盤が必要になる
・石造のアーチ橋の場合、上からの力に強いが横方向の力には弱い
両端に強い力がかかるため、強固な基礎地盤が必要になる
アーチ橋は構造上、両端の部分に強い力(水平反力)がかかります。そのため、補剛桁を用いない無補剛アーチ橋を建設する場合、強固な基礎地盤が必要です。
特に固定アーチと呼ばれる構造形式では、アーチリブの支点部が地面に固定されるため、地盤が軟らかい場所では建設できません。鉄筋コンクリートのアーチ橋は、固定アーチを採用するケースが多く、周辺地盤の条件に左右されます。
ただし、バランスドアーチ橋のように、中間2支点のアーチリブと補剛桁を組み合わせることで、軟弱地盤上に建設可能なアーチ橋も存在します。
石造の場合、上からの力に強いが横方向の力には弱い
石造のアーチ橋は、上からの力に強い一方で、横方向の力に弱いのが欠点です。
大規模な洪水が発生し、横から強い力が加わった場合、変形に耐え切れず破損する恐れがあります。例えば、1982年7月に発生した長崎大水害では、重要文化財である眼鏡橋が半壊し、石材が流失・破損する被害を受けました。
ただし、近代のアーチ橋では、材料に鉄筋コンクリートや鉄鋼を用いることが多く、こうした石造アーチ橋の欠点は克服されています。
アーチ橋の特徴や、メリット・デメリットについて知ろう
アーチ橋は、トラス橋や斜張橋、ラーメン橋などと並ぶ、代表的な橋の構造の一つです。
アーチ橋の部材には、圧縮力のみが作用することから、力学的に安定しているという特徴があります。そのため、橋長100メートル以上の長大橋の建設に適した構造形式です。
またアーチ橋は、周辺の自然環境と調和するため、景観性が高いのもメリットです。実際に日本の重要文化財には、眼鏡橋(長崎県)や錦帯橋(山口県)など、数多くのアーチ橋が選ばれています。
日本でも古くから見られるアーチ橋の特徴や、メリット・デメリットについて知っておきましょう。