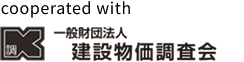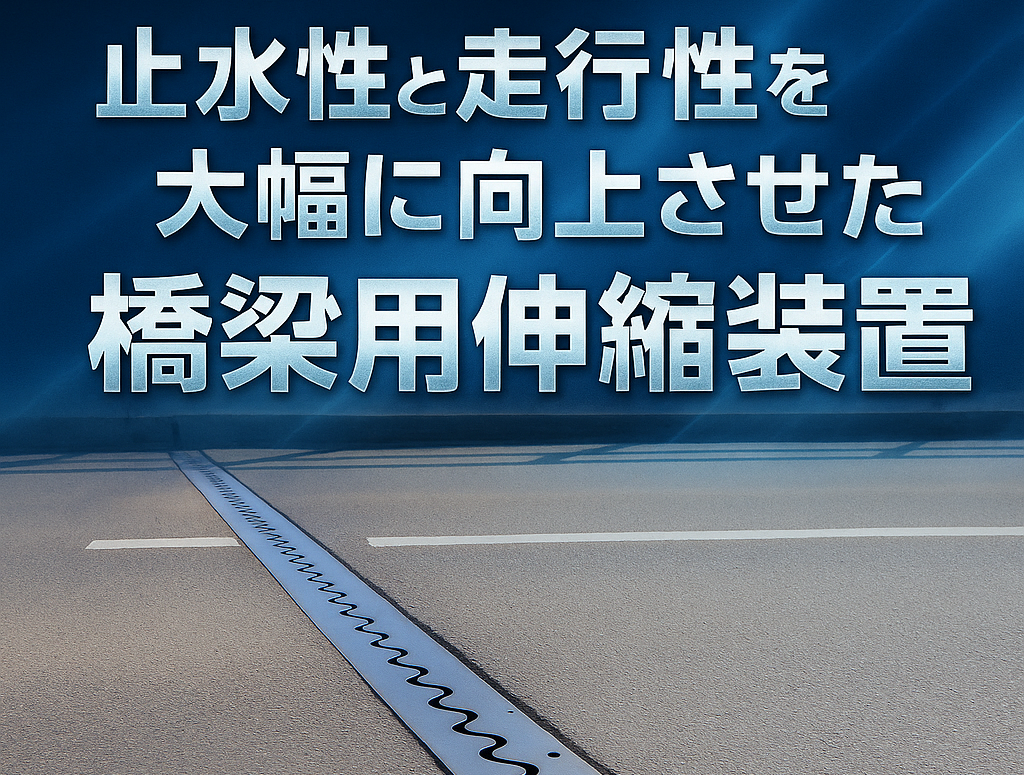COLUMN

支承とは?橋梁における役割や種類を解説
皆さんは、橋がどのようにして支えられているかご存知でしょうか? 巨大な橋桁を支え、地震や温度変化にも耐える重要な役割を担っているのが「支承」です。普段は目立たないですが、橋の安全性を確保する上で欠かせない存在です。本記事では支承について基礎的な内容から種類に関して解説します。
まとめ
- ・支承とは、橋桁と橋脚や橋台との間に設置される、橋桁など上部構造の荷重を下部構造に伝えるための重要な構造部材
- ・役割および機能は、荷重の伝達や温度変化などによる変位の吸収、回転への対応が挙げられる
- ・支承は動き方や素材など切り口によって、分類の仕方が分かれる
支承とは

支承とは、橋桁と橋脚や橋台との間に設置される、橋桁など上部構造の荷重を下部構造に伝えるための重要な構造部材です。
橋の上を車両が通行するたびに荷重がかかり、また、温度変化や地震の影響を受けて橋は常に伸縮したり、わずかに動いたりしています。支承は、これらの動きを吸収することで橋の損傷を防ぎ、安全性を確保します。
支承の主な役割・機能は以下のとおりです。
| 役割・機能 | 説明 |
|---|---|
| 荷重の伝達 | 橋桁の重量や車両の荷重を支える |
| 変位への対応 | 温度変化や地震による橋の伸縮、変位を吸収する |
| 回転への対応 | 上部構造の回転を許容し、構造物に無理な力がかからないようにする |
橋は、支承によって橋台や橋脚に適切に支持されることで、過大な応力が発生することを防ぎ、長寿命化を実現しています。もし支承がなければ、橋桁にひび割れが生じ、最悪の場合は落橋してしまう危険性もあるため、支承は橋の安全性を維持するために必要不可欠な存在なのです。
支承の種類①:動き方による分類
「動き方」の切り口で大きく分けると可動支承、固定支承、免震支承の3つに分類されます。それぞれの特徴や用途について詳しく見ていきましょう。
橋梁の支承は、橋桁を橋脚に支持し、荷重を伝達するための重要な構造要素です。大きく分けると可動支承、固定支承、免震支承の3つに分類されます。それぞれの特徴や用途について詳しく見ていきましょう。
可動支承
橋桁の伸縮や回転を許容する支承です。温度変化や荷重による橋桁の伸縮に対応し、橋脚に無理な力がかからないようにします。
特徴
・橋桁の伸縮、回転を許容
・橋脚への負担を軽減
・維持管理が比較的容易
種類
・ローラー支承: ローラーの転がりによって水平方向の変位を許容する支承
・スライド支承: 滑り面を設けることで水平方向の変位を許容する支承
・球面支承: 球面を介して回転を許容する支承
固定支承
橋桁を橋脚に固定する支承です。橋桁の動きを制限し、橋の安定性を高めます。
特徴
・橋桁を固定し、安定性を確保
・荷重に対する抵抗力が高い
・変位を抑制するため、橋脚への負担が大きくなる場合がある
種類
・ピン支承: ピンを支点として回転のみを許容する支承
・剛結支承: 橋桁と橋脚を一体化させることで、変位を完全に拘束する支承
免震支承
地震の揺れを吸収し、橋梁へのダメージを軽減するための支承です。近年、地震対策として注目されています。
特徴
・地震時の揺れを吸収
・橋梁の損傷を軽減
・耐震性の向上
・他の支承に比べて高価
種類
・積層ゴム支承: 薄い鋼板とゴムシートを交互に積層した支承
・高減衰ゴム支承: 特殊なゴム材料を用いることで、高い減衰性能を持たせた支承
・摩擦振り子支承: 摩擦を利用して地震エネルギーを吸収する支承
支承の種類②:素材による分類
続いて、「素材」の切り口だと鋼製支承とゴム支承の二つに分類されます。
鋼製支承
鋼板や鋼材を組み合わせた支承で、高い強度と耐久性を持ちます。古くから橋梁に用いられてきた実績があり、現在でも多くの橋梁で使用されています。
特徴
・高い強度と耐久性
・荷重や変位に対する安定した性能
・長期的な維持管理の容易さ
種類
・ピン支承: ピンを支点として回転を許容する支承
・ローラー支承: ローラーの転がりによって水平方向の変位を許容する支承
・ロッカー支承: 揺動運動によって水平方向の変位を許容する支承
・スライド支承: 滑り面を設けることで水平方向の変位を許容する支承
ゴム支承
ゴムの弾性を利用した支承で、振動や騒音を吸収する効果に優れています。鋼製支承に比べて軽量で、設置や交換が容易なことも利点です。
特徴
・振動・騒音の吸収効果
・軽量で設置が容易
・経済性
種類
・板ゴム支承: 薄いゴム板を重ねて接着した支承
・積層ゴム支承: 薄い鋼板とゴムシートを交互に積層した支承
・鉛プラグ入り積層ゴム支承: 積層ゴム支承に鉛プラグを挿入することで、地震時のエネルギー吸収能力を高めた支承
支承を選択するにあたって
支承を選ぶ際にはいくつかの重要な基準があります。
まず、橋の規模を考慮する必要があります。規模によって人通りや車の交通量など様々変わってきます。次に、設置場所も重要です。地震や台風が多い地域に耐久力がない支承を選択することは基本的にありません。さらに、支承は橋の重量や交通量に耐えられる設計荷重を満たす必要があります。
経済性も重要な要素です。初期費用だけでなく、長期的な維持管理費用も考慮して支承を選びましょう。最後に、近年では環境負荷の低い材料を使用した支承も注目されています。
これらの要素を総合的に判断し、最適な支承を選定することで、安全で長持ちする橋を建設することができます。
支承の劣化と維持管理
橋梁の支承は、常に交通振動や温度変化、風雨、地震などの影響にさらされています。これらの要因によって、支承は徐々に劣化していきます。適切な維持管理を行わなければ、橋梁全体の安全性に影響を及ぼす可能性があります。
支承の劣化には、以下のような種類があります。
| 劣化の種類 | 現象 |
|---|---|
| ゴムの劣化 | ひび割れ、硬化、膨張、剥離 |
| 鋼材の腐食 | さび、腐食による断面減少 |
| 塗装の劣化 | はく離、変色 |
| アンカーボルトの緩み | 固定力の低下 |
支承の劣化状況を把握するためには、定期的な点検が不可欠です。点検方法は様々ありますが、例としては目視点検、変位測定、非破壊検査などがあります。
また、昨今では建設DX促進によるロボット活用や点群データによる解析も注目を集めています。
・目視点検: 外観の確認、ひび割れや腐食の有無などを目視で確認します。
・変位測定: 支承の変位量を測定し、設計値との比較を行います。
・非破壊検査: 超音波探傷試験などにより、内部の欠陥を検出します。
点検の結果、劣化が確認された場合は、補修または交換などの適切な対策が必要です。軽微な劣化であれば、グリスアップや塗装の塗り替えなどの補修で対応できます。しかし、当然ながら著しい劣化や損傷が認められる場合は、支承全体の交換が必要となります。
最新技術と今後の展望
支承は、安全性・耐久性・経済性・維持管理性など、様々な要求性能を満たすように進化を続けています。
具体的には高性能化・長寿命化においては、より高強度、高耐久性、高耐食性を持つ材料の開発が進んでいます。例えば、繊維強化プラスチック(FRP)や高性能鋼材などを用いた支承は、従来の支承よりも軽量かつ長寿命であることが期待されます。
その他にも構造そのものを改良し、 免震性能や耐久性を向上させる取り組みも進んでいます。例えば、免震支承では、より高い減衰性能を持つダンパーや、より大きな変位に対応できる機構の開発が進められています。
また、支承に限った話ではありませんが、センサー技術や情報通信技術を活用することで、支承の状態をリアルタイムで監視し、異常を早期に検知することが可能になります。これにより、予防保全や維持管理の効率化が期待されます。
まとめ
橋梁を支え、地震や温度変化などの影響から守る支承の役割、種類、維持管理の重要性について解説しました。
支承は常に外部環境にさらされるため劣化しやすく、定期的な点検と適切な維持管理が橋梁の長寿命化に不可欠です。ひび割れや腐食などの兆候を早期に発見し、適切な対策を講じることで、安全性と機能性を維持できます。今後の橋梁建設では、より高性能で長寿命な支承の開発が期待され、技術革新による安全性向上と維持管理の効率化が期待されます。