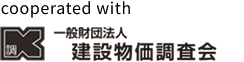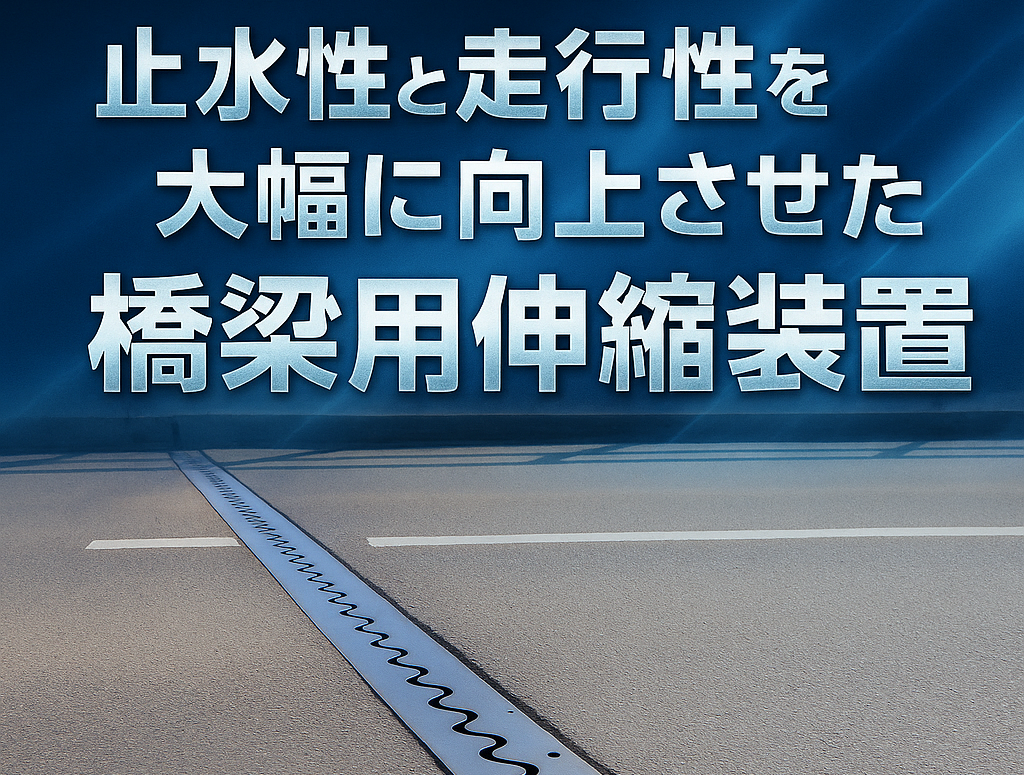COLUMN

橋梁の構造とは?各部材名称や役割を1つずつ解説!
橋梁は、上部構造、下部構造、基礎など、様々な部材が組み合わさって構成されています。それぞれの部材がどのような役割を果たし、どのように連携しているのかを理解することで、橋梁全体の機能や安全性をより深く理解することができます。
次の章では、橋梁の構造とそれぞれの役割について詳しく解説していきます。
まとめ
- ・橋梁の構造は、上部構造と下部構造に大きく分けることができる
- ・上部構造は床版、橋桁、横桁、伸縮装置などから成り立つ
- ・下部構造は橋脚、橋台、基礎から成り立つ
橋梁の構造とそれぞれの役割
橋梁は、上部構造と下部構造に大別できます。上部構造は、橋の上を通る車両や歩行者を支える部分で、下部構造は上部構造を支え、荷重を地盤に伝える役割を担います。それぞれの構造と役割について詳しく見ていきましょう。
上部構造


橋の上部、つまり私たちが普段目にしやすい部分です。主な構成要素は以下の通りです
床版
床版は橋桁の上に設置され、車や人が直接通行する部分です。橋の上部構造において、私たちに最も身近な部分と言えるでしょう。荷重の分散だけでなく、快適な通行を確保する利便性や雨水などが橋桁に浸透するのを防ぐことも重要な役割となります。
橋桁(主桁)
橋桁とは、橋を構成する主要な構造部材の一つで、橋の上部構造を支える水平部材(簡単に言うと一般的に人や車両が通る床版を支える部分)を指します。
橋桁の主な役割は、橋面にかかる荷重(車両や歩行者などの重量、風荷重、雪荷重など)を支え、橋脚や橋台に伝えることです。
横桁
橋桁を横方向(横断する方向)につなぎ、荷重を分散させる役割を担います。橋桁と混合してしまいますが、橋桁は橋の長さ方向に伸びる部材です。横桁が存在することで、横方向にも力が分散される仕組みをとり、橋全体の強度と安定性が高まります。
高欄
高欄とは、橋の両側に設置されている、 人や車が橋から転落するのを防ぐための安全設備です。手すりのような見た目で、橋梁の景観にも大きく関わる部材の1つとなります。
伸縮装置
伸縮装置は橋桁同士の間に設置される装置で、温度変化による橋桁の伸縮を吸収する重要な役割を担っています。橋梁は気温の変化によって伸縮、具体的には夏は膨張し、冬は収縮するのです。もし、この伸縮を吸収する仕組みがなければ、橋桁に大きな負担がかかり、ひび割れや破損などの損傷を引き起こす可能性があります。
伸縮装置は、この伸縮を吸収することで、橋桁への負担を軽減し、橋の長寿命化に貢献しています。
支承
支承とは、橋桁と橋脚や橋台との間に設置される、橋桁など上部構造の荷重を下部構造に伝えるための重要な構造部材です。
橋梁は車両が通行するたびに荷重がかかり、また、温度変化や地震の影響を受けて橋は常に伸縮したり、わずかに動いたりしています。支承は、これらの動きを吸収することで橋の損傷を防ぎ、安全性を確保します。
可動支承・固定支承・免震支承など求める役割によって利用される支承が異なります。詳しくは以下記事で解説しています。
下部構造(橋台、橋脚、基礎)
橋の下部構造は、上部構造を支え、荷重を地盤に伝える重要な役割を担っています。主な構成要素は、橋台、橋脚、基礎の3つです。これらが一体となって橋を安定させ、安全性を確保しています。
橋脚
橋の中間部に位置し、上部構造を支えます。複数設置されることが多く、橋の長さに応じて配置や数が異なります。
橋台
橋の両端部に位置し、土圧や上部構造からの荷重を支えます。また、橋桁の端部を固定または支持する役割も担います。
基礎
橋台や橋脚を支え、地盤に荷重を伝達します。地盤の強度や特性に応じて、適切な基礎形式が選択されます。
基礎には、直接基礎、杭基礎、ケーソン基礎など様々な種類があります。地盤が強固な場合は直接基礎が用いられますが、軟弱地盤の場合は、杭を地中に打ち込む杭基礎や、水中の場合は、大きな箱状の構造物を沈設するケーソン基礎などが採用されます。
橋梁による構造の違い
橋梁は、その構造や材料によって様々な種類に分類されます。ここでは、種類・分類ごとに代表的な橋梁構造の違いをご紹介します。
橋梁の種類による違い
橋梁は、その構造によって様々な種類に分類されます。ここでは、代表的な橋梁の種類を簡単にご紹介します。
桁橋
桁橋は、橋脚や橋台などの支点上に水平に架け渡された桁の上に、床版を設けて荷重を支える構造の橋です。構造が非常にシンプルで建設コストが比較的安価であるため、世界中で最も多く採用されている橋梁形式の一つです。基本的には小型の橋梁となります。
アーチ橋
アーチ橋は、アーチリブ(アーチ状の部材)を利用して荷重を支える構造となっている橋です。その美しい形状から景観にも馴染みやすく、世界各地で古くから建造されてきました。
アーチ橋の力学的特性は、鉛直方向の荷重をアーチの圧縮力に変換することで、橋全体を効率よく支えることです。このため、比較的大規模な橋梁にでも選ばれる種類です。
トラス橋
トラス橋とは、三角形を基本単位として組み合わせた「トラス構造」を主構造とする橋です。三角形は力を分散させるのに優れているため、高い強度と安定性を持ち、長大橋にも適しています。
吊橋
吊橋は、主ケーブルを塔にかけ、そこからハンガーロープで橋桁を吊り下げる構造の橋です。長大スパンの橋梁建設に適しており、優美な外観も特徴です。
斜張橋
斜張橋は、主塔から斜めに張られたケーブルによって橋桁を支える構造の橋です。その優美な外観から、現代的な橋梁の象徴として世界中で人気があります。斜材(ケーブル)は、橋桁の重さを支え、塔に伝える役割を担っています。
ケーブルイグレット橋
ケーブルイグレット橋は、斜張橋と吊橋の特徴を組み合わせた構造形式です。主塔から斜めに張られたケーブル(斜材)で橋桁を支える点では斜張橋と同様ですが、ケーブルイグレット橋では、さらに短いケーブル(イグレット)を主ケーブルから橋桁に直接繋ぎます。このイグレットが、斜材の張力を分散させ、より効率的に橋桁を支える役割を果たします。
ラーメン橋
ラーメン橋は、橋桁と橋脚が一体となった構造を持つ橋のことを指します。ラーメン構造は、部材同士が剛接合されているため、曲げモーメントやせん断力を効率的に分散させることができます。この構造により、長大なスパンを実現することが可能となります。
橋梁の材料による違い
続いては、材料による構造の違いです。
木橋
木橋は、木材を主要な材料として作られた橋です。桁橋、アーチ橋、トラス橋など様々な構造の橋梁で選択されています。
古くから世界中で利用されてきた歴史ある橋梁形式であり、現在でもその温かみのある風合いから、景観に配慮した場所に多く架けられています。比較的小規模の橋梁が多いです。
石橋
石橋は、石を主要な材料として作られた橋です。古くから世界中で建造されております。桁橋やアーチ橋の構造が選択されています。こちらも比較的小規模の橋梁が多いです。
鋼橋
鋼橋は、主材料に鋼を使用した橋です。鋼は強度が高く、大きなスパンの橋を建設できることが特徴です。また、工場で部材を製作し、現場で組み立てるため、工期短縮にも繋がります。
桁橋やアーチ橋、トラス橋だけでなく、ラーメン橋、斜張橋など様々な構造の橋梁で選択されます。
コンクリート橋(無筋・PC橋)
コンクリート橋は、圧縮力に強いコンクリートを主要な材料として作られた橋です。無筋コンクリート橋とプレストレストコンクリート橋(PC橋)に大別されます。
無筋コンクリート橋は、鉄筋を使用しないコンクリートのみで構成された橋です。古くから利用されており、アーチ橋や桁橋などに用いられています。比較的単純な構造で、材料も安価であるため、小規模な橋に向いています。しかし、引張力に弱いため、長スパンの橋には適していません。
一方、PC橋は、コンクリートにあらかじめ圧縮力を加えることで、引張力に対する抵抗力を高めた橋です。これにより、長スパン化が可能となり、現代の橋梁建設において主流となっています。
桁橋やアーチ橋、トラス橋だけでなく、ラーメン橋、斜張橋など様々な構造の橋梁で選択されます。
鉄筋コンクリート橋(RC橋)
鉄筋コンクリート橋(RC橋)は、コンクリートの中に鉄筋を配した構造の橋です。コンクリートの圧縮強度と鉄筋の引張強度を組み合わせることで、高い強度と耐久性を実現しています。20世紀に入り広く普及し、現在でも多くの橋梁で採用されている、代表的な橋梁形式の一つです。
桁橋やアーチ橋、トラス橋だけでなく、ラーメン橋、斜張橋など様々な構造の橋梁で選択されます。
複合橋
複合橋とは、異なる材料を組み合わせて建設された橋のことを指します。それぞれの材料のメリットを活かし、デメリットを補うことで、より優れた性能を発揮できます。代表的な組み合わせとしては、鋼橋とコンクリート橋を組み合わせた「鋼コンクリート複合橋」があります。
桁橋やアーチ橋、トラス橋だけでなく、ラーメン橋、斜張橋など様々な構造の橋梁で選択されます。
まとめ
本記事では、橋梁の上部構造と下部構造のそれぞれを構成する部材の名称と役割について解説しました。橋桁や床版、橋脚や基礎など、それぞれの部材がどのように機能し、橋梁全体の強度と安定性を支えているのかを理解することで、普段利用している橋梁の意外な側面をご理解いただければ幸いです。