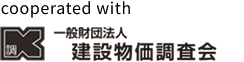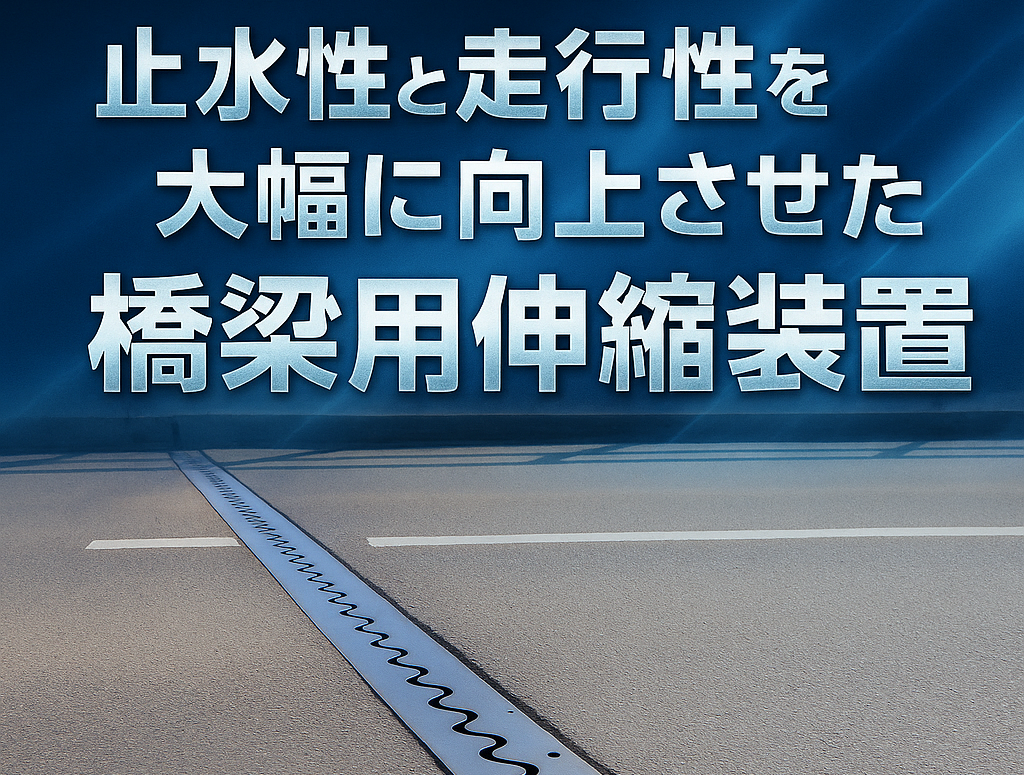COLUMN

斜張橋とは?構造や仕組み、作り方を詳しく解説!
主塔から斜めにケーブルを張り、荷重を支える橋のことを斜張橋(しゃちょうきょう)と言います。斜張橋は長大橋の建設に適しており、支間長が800メートルを超える橋の建設も可能です。
なぜ細いケーブルによって橋を支えられるのか、気になる方もいるでしょう。この記事では、斜張橋の構造や荷重を支える仕組み、代表的な作り方・架設工法について詳しく解説します。
まとめ
- ・斜張橋とは主塔から斜めにケーブルを張った橋のこと
- ・斜張橋の構造は大きく、主塔・ケーブル・桁の3つで成り立つ
- ・近年の斜張橋は、PC斜張橋を採用することが一般的
斜張橋とは

斜張橋とは、“主塔から斜め直線状に張ったケーブルで補剛桁の中間部を吊った形式の橋梁”を指します。
多数のケーブルで橋を吊り上げるため、桁の部分の部材重量を軽減できるのが特徴です。桁高が小さく、桁下空間にゆとりのあるスリムな橋を建設できます。
橋の構造形式には、桁橋やアーチ橋、トラス橋などの種類がありますが、斜張橋は長大橋の建設に最も適しています。例えば、1999年5月に開通した多々羅大橋は、最大支間長が890メートル、橋長1,480メートルと、完成当時は世界最長の斜張橋でした。
また神戸市では、六甲アイランドとポートアイランドを結ぶ連続斜張橋の建設が計画されており、完成すれば世界最大規模の斜張橋となる予定です。
斜張橋は3種類ある
斜張橋は、主塔から伸びるケーブルの張り方によって、放射型・ファン型・ハープ型の3種類に分かれます。
| 斜張橋の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 放射型(ラジアル型) | 主塔の先端から、放射状にケーブルが伸びる |
| ファン型(扇型) | 主塔のケーブル定着部がずれ、扇状にケーブルが広がる |
| ハープ型 | 主塔のケーブル定着部が等間隔にずれ、平行にケーブルが伸びる |
放射型(ラジアル型)
放射型は、ラジアル型とも呼ばれ、ケーブルが主塔の先端から放射状に伸びる斜張橋です。
塔頂にケーブルが集まるため、ケーブルの本数が少ない小型の斜張橋に適しています。主塔の高さに比例してケーブルの角度が大きくなるため、垂直方向に強い力がかかるのが欠点です。
例えば、広島県尾道市にある尾道大橋(おのみちおおはし)が、放射型の斜張橋の一例です。尾道大橋は1968年に完成し、最大支間長が200メートルを超える日本初の斜張橋として、一躍注目を集めました。
ファン型(扇型)

ファン型は、主塔のケーブル定着部が上下方向に少しずつずれた斜張橋です。ケーブルが扇状に広がって見えることから、「扇型」とも呼ばれます。
例えば、東京港と横浜港を結ぶ横浜ベイブリッジも、ファン型の斜張橋です。横浜ベイブリッジは、ケーブルが張り出すタワーが2本あり、上層が首都高速道路、下層が国道357号線の2層構造になっています。
ハープ型
ハープ型は、主塔のケーブル定着部が等間隔にずれ、ケーブルが平行に伸びた斜張橋です。ファン型と並んで、近年の斜張橋によく見られる形式です。ハープのような美しいデザインから、景観性にも優れています。
ハープ型の斜張橋の一例が、1996年に完成した十勝大橋(新十勝大橋)です。橋長501メートル、幅員は32メートルと非常に広く、2本の主塔からハープ型のケーブルが張られています。
斜張橋と吊橋の違い
斜張橋とよく似ているのが、吊橋です。斜張橋と吊橋には、以下のような違いがあります。
| 斜張橋 | 吊橋 | |
|---|---|---|
| ケーブル | 主塔と桁が直結され、ケーブルが斜め方向に伸びる | 主塔の間にメインケーブルを架け渡し、垂らしたハンガーロープが桁を吊り上げる |
| アンカーブロック | ケーブルを定着するアンカーブロックが不要 | 両端にアンカーブロック、またはアンカレイジと呼ばれる重しが必要 |
| 塔の高さ | 同じスパンの橋の場合、吊橋より塔の高さは高くなる | 斜張橋と比べ、塔の高さは低くなる |
| 桁にかかる力 | 張力(垂直方向にかかる力)、圧縮力(橋軸方向にかかる力) | 張力のみ |
斜張橋の構造は?主塔・ケーブル・桁の役割を解説
斜張橋は、主塔・ケーブル・桁の3つの部分で成り立っています。ここでは、それぞれの役割を解説します。
主塔
主塔とは、斜張橋を支えるケーブルが張り出す塔です。
通常、主塔の本数は2本であることが多いですが、主塔が1本の斜張橋や、3本以上の斜張橋も存在しています。主塔の形状もさまざまで、A字形や逆Y字形、門形などがあります。
主塔には、両側に張られたケーブルを通じて圧縮力が作用するため、主塔の材料には圧縮強度が高い鉄筋コンクリート(RC)の他、鋼材が用いられることが一般的です。
ケーブル
ケーブルは斜材とも呼ばれ、吊橋や斜張橋などにおいて、鋼線を束ねて引張部材として用いたもののことを指します。
ケーブルを張る面数は、1面または2面であることが一般的です。1面の斜張橋では、桁の中央に1本の主塔を建ててケーブルを張ります。2面の場合は、桁に2本組みの主塔を設置し、左右の主塔からケーブルを張り出します。
桁(主桁)
桁とは、橋桁や主桁、補剛桁とも言い、人や車が通行する部分を指す言葉です。斜張橋の場合、トラス構造の桁か、箱形の桁を採用することが一般的です。補剛桁がトラス構造の場合、補剛トラスと呼ばれます。
左右で力のつり合いを取るため、桁の長さは中央の主塔を基準として、1対1となるように設計することが一般的です。主塔が2本の斜張橋では、側径間(主塔の側方部分の区間)と中央径間(2本の主塔の間にある区間)の比率が、通常は1対2になります。
ただし、側径間を重いコンクリート桁(PC桁)、中央径間を軽い鋼桁とし、中央支間長を伸ばす例もあります。
斜張橋が荷重を支える仕組み
斜張橋は、細いケーブルでなぜ橋全体の荷重を支えられるのでしょうか。ここでは、斜張橋の仕組みを紹介します。
斜めに張ったケーブルで橋桁を弾性的に支える
斜張橋は、主塔から斜め直線状に張ったケーブルにより、橋桁を弾性的に支える仕組みです。
主塔と桁を直結するケーブルには、大きな張力が生じます。この張力は、ケーブル側の固定点では垂直方向の力、主桁側の固定点では橋軸方向の力(主桁を主塔へ引き寄せる、水平方向の力)に変換されます。水平の桁橋で大きくなりがちな「曲げモーメント」(橋の構造物や部材を曲げようとする力)が発生しないため、力学的に安定性の高い構造です。
また主塔では、左右に伸びるケーブルによって、水平方向に力がつり合います。そのため、吊橋のようにアンカーブロックやアンカレイジを両端に設置し、左右のバランスを調整する必要はありません。
近年は風に対する安定性も高まっている
斜張橋は多数のケーブルによって橋全体を吊り上げるため、桁の部分は比較的軽量となるように設計されることが一般的です。桁下空間も広いため、風に対する安定性が低いという欠点があります。
しかし近年は、主桁にフェアリングプレートやスプリッタープレートと呼ばれる部材を取り付けるなどの対策が行われています。神戸港に架かる東神戸大橋のように、橋桁を補剛トラスにすることでも、耐風安定性を高めることが可能です。
また斜張橋のケーブルに大きな張力が働くことも、風の影響を受けやすい原因の一つです。特に雨混じりの風が吹くと、レインバイブレーションと呼ばれるケーブルの共振現象が発生する可能性があり危険です。
そのため、斜張橋にはケーブルの振動を抑制するための工夫も見られます。例えば天保山大橋では、主桁のフェアリングプレート内に制振ダンパーを設置し、ケーブルの振動を軽減しています。
斜張橋の代表的な作り方・架設工法
近年の斜張橋は、PC斜張橋を採用することが一般的です。日本での施工例は少ないものの、海外では経済性や工期の面から、合成斜張橋と呼ばれる工法を採用するケースもあります。また斜張橋とは異なりますが、よく似た工法にエクストラドーズド橋があります。
以下で、PC斜張橋、合成斜張橋、エクストラドーズド橋のそれぞれの作り方・架設工法の違いを紹介します。
PC斜張橋

PC斜張橋とは、主桁の材料にプレストレストコンクリート(PC)を用いる斜張橋です。プレストレストコンクリートとは、PC鋼材に張力(緊張力)を与えてからコンクリートに固着させた材料です。圧縮力に強いコンクリートと、引張力に強いPC鋼材の組み合わせにより、高い強度があります。
PC斜張橋の場合、ケーブルの配置形状はファン型かハープ型のいずれかであることが一般的です。施工の際は、主塔を建設しケーブルを張り渡しながら、張出し架設工法によって主桁を伸ばしていきます。
合成斜張橋
合成斜張橋とは、鋼桁とコンクリート桁を合成した、合成桁(連続桁)を用いる主桁斜張橋です。
PC斜張橋と比べ、橋桁の軽量化が可能です。また鋼桁のみを用いる鋼斜張橋よりも、経済性に優れるという強みがあります。
エクストラドーズド橋
エクストラドーズド橋は、斜張橋と桁橋の特徴を併せ持つ架設工法です。
エクストラドーズド橋にも、斜張橋のような主塔やケーブルがありますが、橋全体の荷重を支える上で主桁の剛性がより重要です。外見上は、斜張橋よりも主塔の高さが低く、ケーブルの角度も水平に近くなっています。
斜張橋と比較すると、ケーブルの疲労強度(繰り返し力がかかったときの壊れにくさ)が高い構造になっているため、ケーブルの本数を削減できます。長大橋の建設には適していませんが、斜張橋と比べ建設コストが低い工法です。
長大橋の建設に適した斜張橋の構造や仕組みを知ろう
斜張橋は、主塔から斜め直線状に張った多数のケーブルで桁を吊り上げ、橋全体を支える構造形式です。長大橋の建設に適しており、多々羅大橋のように支間長が800メートルを超える斜張橋も存在します。
斜張橋の構造は、主塔・ケーブル・桁の3つの部分で成り立っています。主塔から左右に伸びるケーブルによって、水平方向に力がつり合うため、吊橋と異なり両端にアンカーブロックを設置する必要がありません。
斜張橋の構造や仕組み、代表的な架設工法について知っておきましょう。