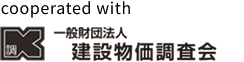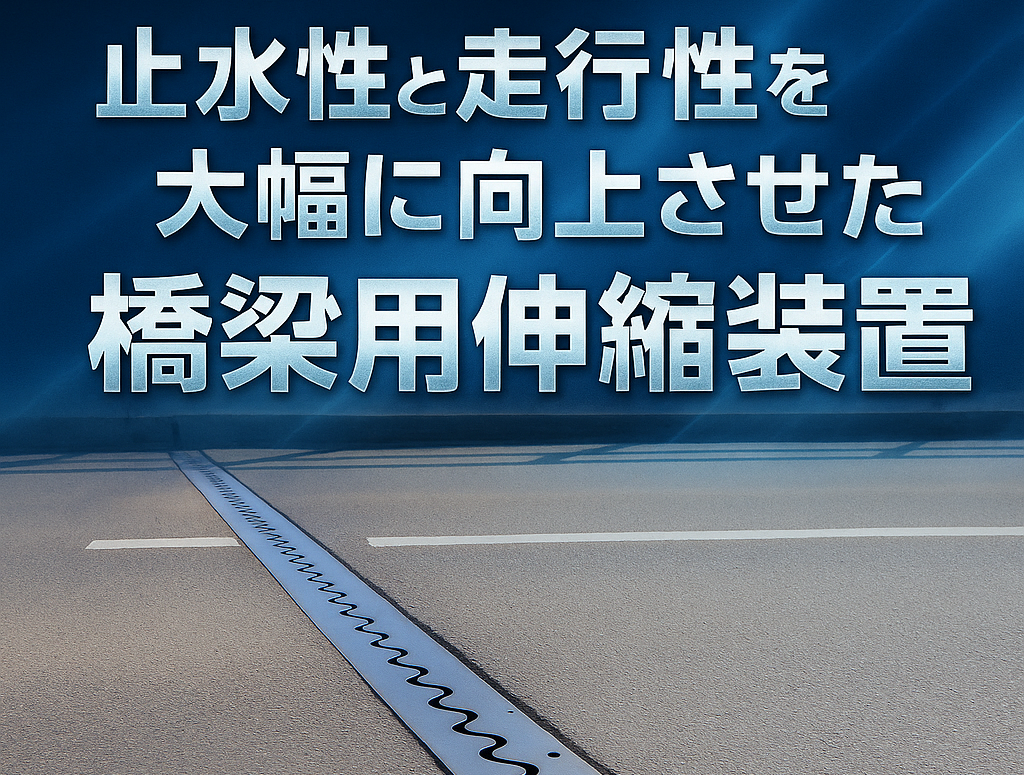COLUMN

斜張橋の特徴とは?メリット・デメリットを詳しく解説
斜張橋(しゃちょうきょう)は、“塔から斜めに張られた複数のケーブルで吊り、支える構造の橋”です。水平な橋桁で荷重を支える桁橋と比べ、長支間の橋の建設に適しています。
よく似た構造形式に吊橋がありますが、斜張橋と吊橋はさまざまな点で違いがあります。設計上の自由度の高さや、維持管理の容易さなど、斜張橋ならではの利点を知っておきましょう。
この記事では、斜張橋の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。
まとめ
- ・斜張橋は、水平な橋桁で荷重を支える桁橋と比べ、長支間の橋の建設に適している
- ・斜張橋のメリットは、設計上の自由度が高いことや景観が高いことなどが挙げられる
- ・斜張橋のデメリットは、風の影響を受けやすい構造である故の破損やケーブルの共振現象により破損が早まるなどがあり、対策の余地がある
斜張橋に見られる3つの特徴

斜張橋は、日本では1950年代の終わり頃に建設が始まりました。初期の斜張橋として、神奈川県の相模湖に架かる勝瀬橋(1959年_上記の画像)や、最大支間が200メートルを超える尾道大橋(1968年)などの例が有名です。
そのような斜張橋には、3つの特徴があります。ここでは、斜張橋が荷重を支える仕組みや、どのような場所に採用されるかを紹介します。
・主塔と桁をケーブルで直結して支える
・桁高が小さく、桁下空間を確保できる
・長支間の橋が必要な場所に建てられることが多い
主塔と桁をケーブルで直結して支える
斜張橋は、主塔から斜めにケーブルを張り、ケーブルの張力によって桁(橋桁)を支える仕組みになっています。一見、吊橋とよく似ていますが、ケーブルの張り方が大きく異なります。
| 斜張橋 |  ・主塔と桁をケーブルで直結する ・桁が斜め方向のケーブルで支えられるため、垂直方向の張力だけでなく、橋軸方向の圧縮力がかかる |
|---|---|
| 吊橋 |  ・主塔をメインケーブルで結び、そこから垂らしたハンガーロープで桁を吊り上げる ・桁には垂直方向の張力のみがかかる |
吊橋では、メインケーブルから垂らしたハンガーロープで桁を吊り上げます。桁の部分には、垂直方向の張力(桁を引っ張り上げる力)しか作用しません。しかし、橋の両側でメインケーブルを繋ぎ止めるため、アンカーブロックまたはアンカレイジと呼ばれる重しを設置する必要があります。
一方、斜張橋は斜めに張られたケーブルが桁を支えており、垂直方向の張力に加えて、内側(橋軸方向)への圧縮力も作用します。桁に働く圧縮力が、ケーブルに働く引張力と塔の左右でつり合うため、ケーブル定着用のアンカーブロックは不要です。そのため、アンカーブロックの設置が困難な軟弱地盤にも建設できます。
桁高が小さく、桁下空間を確保できる
斜張橋は桁橋と比べると、橋桁に大きな剛性が求められません。そのため、桁高が小さく、軽量でスレンダーな橋桁を採用できます。桁下空間を広く確保できるため、多くの船舶が行き交う港湾部の橋に適しています。
例えば、横浜港のランドマークである横浜ベイブリッジも、上下2層構造になった斜張橋です。また長崎港にある女神大橋(ヴィーナスウィング)では、大型船舶の航行を想定し、桁下65メートルの高さを確保しています。
長支間の橋が必要な場所に建てられることが多い
斜張橋は桁橋と比べ、長支間の橋の建設に適した構造形式です。
・多数のケーブルにより桁を吊り上げるため、構造上の安定性が高い
・橋桁が比較的軽量なため、桁橋よりも経済的に長支間化できる
・斜めに張られたケーブルを利用し、張出し架設工法で容易に橋桁を延長できる
以上のような理由から、斜張橋は支間長が300~500メートルとなる場所に建てられることが一般的です。近年は長大橋の建設に当たって、トラス橋(港大橋など)ではなく斜張橋を採用するケースも増えています。
斜張橋の3つのメリット
他の構造形式と比べると、斜張橋には3つのメリットがあります。
・設計上の自由度が大きい
・PC斜張橋はメンテナンス性が高い
・景観性が高く、ランドマークとして利用できる
設計上の自由度が大きい
斜張橋の1つ目のメリットは、設計上の自由度の大きさです。斜張橋は、支間長が500~600メートルを超えるような長大橋を除き、ケーブルの張り方や主塔の形状・本数などを自由に選べます。
| ケーブルの張り形式 | 放射型(ラジアル型)、ファン型(扇型)、ハープ型 |
|---|---|
| 主塔の本数 | 1本(幸魂大橋など)、2本(横浜ベイブリッジ、十勝大橋など)、3本以上(クイーンズフェリー・クロッシング橋など) |
| 主塔の形状 | 1本柱形、独立2本柱形、A形、逆Y形、H形 |
例えば、主なケーブルの張り方には、放射型(ラジアル型)、ファン型(扇型)、ハープ型の3種類があります。ケーブルの張り方を変えることにより、ケーブルの疲労強度や、桁にかかる張力の大きさなどを調節可能です。
主塔の本数は2本が一般的ですが、主塔が1本しかないものや、3本以上あるものも存在します。例えば、大阪湾岸道路の延伸部では、新たに主塔が3本以上の斜張橋(六甲アイランド~ポートアイランド間)や、1本の斜張橋(ポートアイランド~和田岬間)の建設が進んでいます。
また主塔の形状も、1本柱形や独立2本柱形、A形、逆Y形、H形など、さまざまな選択肢から選ぶことが可能です。周辺の地形や景観に合わせ、自由度の高い設計が可能である点も斜張橋の魅力です。
PC斜張橋はメンテナンス性が高い
斜張橋の2つ目のメリットは、PC斜張橋のメンテナンス性の高さです。
PC斜張橋とは、主桁の材料にプレストレスト・コンクリート(PC)を用いた橋を指します。主塔には鉄筋コンクリート(RC)、ケーブルにはPC鋼材など、材料の特性を活かした設計が行われることが一般的です。欧米ではPC斜張橋か、鋼桁とコンクリート桁を複合した合成斜張橋が広く普及しています。
斜張橋は主塔やケーブルなど、部材の数が多く、メンテナンスに手間がかかると言われています。特に鋼斜張橋は、主要部材の腐食や塗装の劣化、ボルト類の傷みなどにより、維持管理にコストがかかるのが欠点です。
しかしPC斜張橋は、鋼斜張橋と比べ維持管理が容易であり、メンテナンス費用も比較的安価です。橋全体の剛性も高いことから、国内でも鋼斜張橋に代わり、PC斜張橋の建設が増えつつあります。
景観性が高く、ランドマークとして利用できる
斜張橋の3つ目のメリットは、景観性の高さです。スレンダーな橋桁や、主塔の造形、斜めに張られたケーブルが生み出す造形上の美しさなどから、地域のランドマークとして利用される例もあります。
例えば、長崎港を結ぶ女神大橋(ヴィーナスウィング)は、夜になるとライトアップされ、長崎市の夜景のシンボルとなっています。その美しさから、日本夜景遺産(ライトアップ夜景遺産)に選ばれた他、2021年11月には長崎市全体がモナコ・上海とともに「世界新三大夜景」都市に認定されました。
斜張橋の3つのデメリット
一方、斜張橋にはデメリットも3つあります。
・風の影響を受けやすい構造をしている
・ケーブルの共振現象が起きる可能性がある
・吊橋よりも塔を高く設計する必要がある
風の影響を受けやすい構造をしている
斜張橋の1つ目のデメリットは、風による影響の受けやすさです。
斜張橋は比較的軽量な橋桁を用いることから、強風時にたわみやすく、風に対する安定性が低い構造をしています。例えば、愛媛県の離島を結ぶ岩城橋では、風の影響により振動が発生した結果、開通からわずか2年で全17基の照明柱のうち12基に亀裂が生じました。
近年は斜張橋の耐風安定性を高めるため、さまざまな技術が導入されています。例えば、神戸港に架かる東神戸大橋では、塔頂に制振装置を設け、風による微震動を抑制しています。
また近年増加しているPC斜張橋も、橋全体に重量があり、剛性も高いことから、吊橋や鋼斜張橋と比べ耐風安定性が高いと言える部分もある構造形式です。
ケーブルの共振現象が起きる可能性がある
斜張橋の2つ目のデメリットは、ケーブルの共振現象が起きるリスクです。
斜張橋には多くのケーブルが張られているため、雨を伴う風が吹くとケーブル表面を水滴が伝い落ち、レインバイブレーションと呼ばれる振動を引き起こす可能性があります。レインバイブレーションは、主塔のケーブル定着部分を疲労させる他、景観を大きく損ねかねないことから、斜張橋における課題の一つです。
国内の斜張橋では、レインバイブレーションを抑制するため、さまざまな対策が導入されています。例えば、ケーブル定着部分への制振ダンパーの設置(天保山大橋など)や、ケーブルの表面に突起を設ける(東神戸大橋など)といった工夫が一例です。
吊橋よりも塔を高く設計する必要がある
斜張橋の3つ目のデメリットは、主塔の高さの制限です。同じスパン(注)の橋を建設する場合、斜張橋は吊橋と比べ、塔をやや高く設計する必要があります。
注:スパンとは、支間長とも言い、橋脚から橋脚までの間の距離を意味します。
前述のとおり、斜張橋の桁には垂直方向の張力だけでなく、橋軸方向の圧縮力が作用します。斜張橋のスパンが長くなるほど、内向きの圧縮力が大きくなるため、主塔を高くして力のつり合いを取る必要があります。しかし、塔を高くしすぎても不安定になるため、支間長が1,000メートルを超えるような橋の建設にはあまり適していません。
一方、吊橋は斜張橋と異なり、桁には垂直方向の張力しか作用しません。そのため周辺の地形条件にもよるものの、斜張橋よりも長いスパンでの建設が可能です。
実際に国内でも、最大支間長が1,000メートルを超える長大橋のほとんどは、斜張橋ではなく吊橋です。
斜張橋の特徴やメリット・デメリットについて知ろう
斜張橋は、日本国内で広く見られる橋の構造形式の一つです。主塔からケーブルを斜めに張り、橋桁を吊り上げるのが特徴です。
多数のケーブルによって重量を支えるため、シンプルな構造の桁橋と比べ、長支間の橋の建設に適しています。景観性にも優れており、横浜ベイブリッジや女神大橋のように、地域のランドマークとして利用される斜張橋も少なくありません。斜張橋は吊橋とよく似ていますが、より剛性が高く、アンカーブロックの設置も不要です。ただし、支間長が1,000メートルを超えるような橋の建設には、吊橋のほうが適しています。斜張橋の特徴や、他の橋と比べたメリット・デメリットについて知っておきましょう。