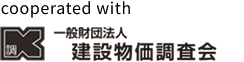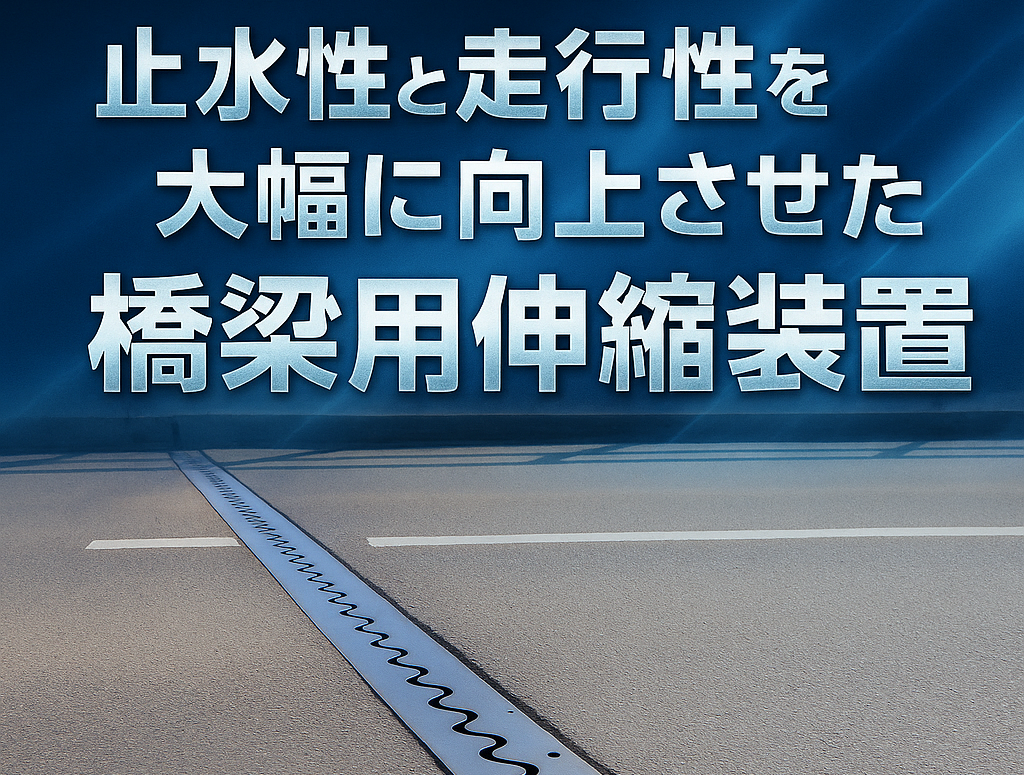COLUMN

トラス橋とは?構造や仕組み、作り方を詳しく解説!
トラス橋(きょう)は、アーチ橋や吊り橋などと並んで、日本でも広く見られる橋の構造形式です。
なぜトラス橋が盛んに建設されているのか、気になる方も多いでしょう。この記事では、トラス橋に用いられる「トラス構造」の仕組みや、代表的な作り方・架設工法について紹介します。
まとめ
- ・トラス橋とは、”直線状の部材を三角形に組み合わせるトラス構造を採用した橋
- ・構造上、力学的に安定しているため外から力が加わっても変形しにくく、さらに重量が軽いという特徴がある
- ・トラス橋のメリットは、橋桁を曲げや変形に強くし、一般的な桁橋よりも支間長(橋台や橋脚の間隔)を長くすることが可能
目次
トラス橋とは?

トラス橋とは、”直線状の部材を三角形に組み合わせるトラス構造を採用した橋”を指します。
トラス構造は棒状の部材を組み合わせて作られた、三角形の集合体です。力学的に安定しているため、外から力が加わっても変形しにくく、さらに重量が軽いという特徴があります。
例えば、東京湾で2012年に開通した東京ゲートブリッジ(直前の画像)も、橋梁区間が2,618メートルに及ぶトラス橋です。
軽くて丈夫なトラス構造は、古くからさまざまな建造物に採用されてきました。例えば、19世紀末に完成したパリのエッフェル塔も、大部分がトラス構造です。
橋の建設にもトラス構造を採用することで、橋桁を曲げや変形に強くし、一般的な桁橋よりも支間長(橋台や橋脚の間隔)を長くできます。日本でも数多くのトラス橋が建設されており、中には橋長2,618メートルの東京ゲートブリッジを超える支間長の橋も存在します。
日本におけるトラス橋の例
日本では、明治時代になって初めて鉄の橋が架けられました。鉄製のトラス橋も明治初期から盛んに建設され、1877年には日本最初の複線用鉄橋である六郷川鉄橋(愛知県)が架設されています。
ここでは、日本におけるトラス橋の例を3つ紹介します。
・港大橋(大阪府)
・旧揖斐川橋梁(岐阜県)
・南河内橋(福岡県)
港大橋(大阪府)

大阪府大阪市にある港大橋は、日本最大の支間長を誇るトラス橋です。中央部の支間長は東京ゲートブリッジより長く、510メートルにのぼります。
また港大橋は、大阪港のランドマークとして長年大きな存在感を発揮してきました。赤一色に塗装されたデザインや、大阪港を一望できる景色から、浪速の名橋50選にも選定されています。
大阪港には当初、両岸の主塔から斜め直線状にケーブルを張る斜張橋(斜張橋)が建設される予定でした。しかし、軟弱な地盤への影響や、工期の問題からトラス橋に計画を変更しています。
旧揖斐川橋梁(岐阜県)

岐阜県大垣市の揖斐川に架かる旧揖斐川橋梁は、明治19年に竣工した鉄製五連トラス桁橋です。橋長は325.1メートル、トラス桁の長さは63.6メートルと、当時としては最大級のものでした。
明治期に建設された鉄道橋には、イギリスから輸入された近代的な鉄道技術の影響が色濃く見られます。特に旧揖斐川橋梁には、鉄道技術史上、高い歴史的価値があることから、2008年に重要文化財の指定を受けています。
南河内橋(福岡県)

福岡県北九州市の南河内橋も、重要文化財に指定された鋼製二連トラス橋です。大蔵川上流に位置する道路橋で、大正15年に完成しています。
近代日本で唯一のレンティキュラートラス構造を採用しており、真横から見ると凸レンズのように見えるのが特徴です。
トラス橋にはどんな構造がある?代表的なものを解説
トラス橋には、さまざまなトラス構造が採用されています。トラスの基本的な組み方は、ハウトラス、プラットトラス、ワーレントラスの3つです。
ここでは、トラス橋に見られる代表的なトラス構造を紹介します。
| 主なトラス構造 | 例 |
|---|---|
| ハウトラス | ハウトラス |
| プラットトラス | プラットトラス、曲弦プラットトラス |
| ワーレントラス | ワーレントラス、曲弦ワーレントラス、垂直材(鉛直材)付きワーレントラス、ダブルワーレントラス |
| その他のトラス構造 | ペンシルヴァニアトラス、ボルチモアトラス、Kトラス、クイーンポストトラス、キングポストトラス |
ハウトラス
ハウトラスとは、斜材(注)をハの字に配置したトラス構造を指します。例えば、三陸鉄道の安家川橋梁(岩手県)が、ハウトラスを採用したトラス橋の一例です。
注:斜材とは、骨組構造において斜めに配置された部材の総称で、一般的にはトラス構造の上下の部材を斜めにつなぐ部材を指します。
ハウトラスの特徴は、斜材が圧縮材(上から荷重がかかると、圧縮力を受ける部材)として働く点です。そのため、圧縮力に強いプレストレスト・コンクリート(PC)を用いたPCトラス橋の建設に適しています。また古くは、木造トラス橋にもハウトラス構造が多く見られました。
プラットトラス
プラットトラスとは、斜材を逆八の字に配置したトラス構造です。例えば、九州本土と天草諸島を結ぶ天草五橋(1号橋)が、プラットトラスを採用したトラス橋の一例です。
ハウトラスとは対照的に、プラットトラスでは斜材が引張材(上から荷重がかかると、引っ張られて伸びる部材)として機能します。そのため、圧縮力に対して強い一方、引張力に弱いコンクリート材を用いることは基本的にありません。
プラットトラスは、主に鋼トラス橋の建設に採用されることが多いトラス構造です。プラットトラスの他にも、トラスの上部がゆるやかなアーチを描く「曲弦プラットトラス」などの類例があります。
ワーレントラス
ワーレントラスとは、斜材の向きが交互に入れ替わるトラス構造です。例えば、常磐新線(つくばエクスプレス)が運行するつくば荒川橋梁が、ワーレントラスを採用したトラス橋の一例です。
ワーレントラスでは、斜材がパネル(三角形)によって圧縮材の役割を果たしたり、引張材の役割を果たしたりします。力学的な安定性が高く、垂直材(鉛直材)を用いずに建設できます。近年では、垂直材を用いないトラス橋をワーレントラスと呼ぶことが一般的です。
その他、ワーレントラスには以下のような類例があります。
・垂直材(鉛直材)付きワーレントラス
・曲弦ワーレントラス
・ダブルワーレントラス
曲弦ワーレントラスは上部がアーチ型をしており、一見するとアーチ橋と見分けがつかない場合もあります。またワーレントラスの中でも、斜材をX形に重ね合わせるものをダブルワーレントラスと呼んで区別します。
その他のトラス構造
その他、身近な鉄道橋などではあまり見かけませんが、以下のようなトラス構造があります。
・ペンシルヴァニアトラス
・ボルチモアトラス
・Kトラス
・クイーンポストトラス
・キングポストトラス
例えば、Kトラスは英字のKによく似た形でトラスを組む構造です。またクイーンポストトラスやキングポストトラスのように、現在では建物の屋根などの建設に用いられるトラス構造もあります。
トラス橋の仕組みは?軽くて丈夫と言われる理由
トラス橋の強度が高いと言われる理由は、主構造であるトラス構造にあります。
前述のとおり、トラス構造は三角形を組み合わせた構造です。三角形は、多角形の中でも内部的に安定しており、外から力が加わっても変形しにくいという特徴があります。
例えば、四角形の構造物(ラーメン構造など)に上から力を加えると、部材に曲げモーメント(注)が作用します(※)。一方、三角形の構造物に荷重をかけても、部材には軸力(引っ張ったり圧縮したりする力)しかかかりません。
注:曲げモーメントとは、“構造物や部材に曲げ変形を生じさせようとする力”を指します。
一般的に、曲げモーメントがかかる部材と比べ、軸力しか作用しない部材は、断面積を小さくできます。トラス構造が軽くて丈夫とされるのも、この三角形の構造力学的な安定性によるものです。
トラス橋の主な作り方・架設工法を紹介
今日では移動式クレーン(トラッククレーン)や、組み立て式のトラベラクレーンなどの重機を用いて、トラス橋を架設することが一般的です。
ここでは、トラス橋の作り方・架設工法を2つ紹介します。
・ベント工法(自走クレーンベント工法、トラッククレーンベント工法)
・トラベラクレーン工法(トラベラクレーン片持ち式工法)
ベント工法(自走クレーンベント工法)
ベント工法とは、自走クレーンベント工法やトラッククレーンベント工法とも呼ばれ、橋梁の建設に用いられる一般的な架設工法です。桁ブロックの継ぎ手付近に鋼製脚(ベント)を仮設することから、ベント工法と呼ばれます。
ベント工法の手順は以下のとおりです。
1.桁ブロックの継ぎ手の直下にベントを設置する
2.運搬されてきた部材(架設桁)を移動式クレーンで吊り上げ、架設していく
3.ボルトまたは溶接で架設桁を連結したら、ベントを解体する
ベント工法には、他の工法と比べ工期が短く、工費も少ないというメリットがあります。またトラス橋をはじめとして、さまざまな構造形式の橋の架設に適しています。
トラス橋の場合、側径間(橋の両端にある、橋台に隣接した区間)をベント工法で施工し、中央径間(橋中央の区間)には他の工法を用いることが一般的です。
トラベラクレーン片持ち式工法
トラベラクレーン工法は、山間部や河川など地形条件が厳しく、桁下に移動式クレーンを設置できない場合に採用される工法です。まず陸上部の数ブロックを移動式クレーンで架設した後、橋桁の上でトラベラクレーンを組み立て、部材を吊り上げながら残りの区間を架設していきます。
トラベラクレーン工法は、トラス橋の建設にも適しています。特にトラス桁が長く、ベント工法のみでの架設が難しい場合は、トラベラクレーン工法を併用するケースが一般的です。
トラス橋の種類や変形に強い理由について知ろう
トラス橋は、日本でも明治時代から採用されてきた橋の構造形式です。三角形を組み合わせたトラス構造を主構造としており、軽くて丈夫という強みがあります。
トラス構造には、ハウトラスやプラットトラス、ワーレントラスなど、さまざまな種類があります。例えば、PCトラス橋ではハウトラス、鋼トラス橋ではプラットトラスを採用することが一般的です。
トラス橋の建設には、ベント工法やトラベラクレーン工法など、通常の橋梁工事と同様の架設工法が用いられます。ただし、東京ゲートブリッジのように、クレーン船を用いて架設した事例もあります。