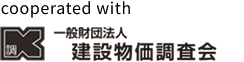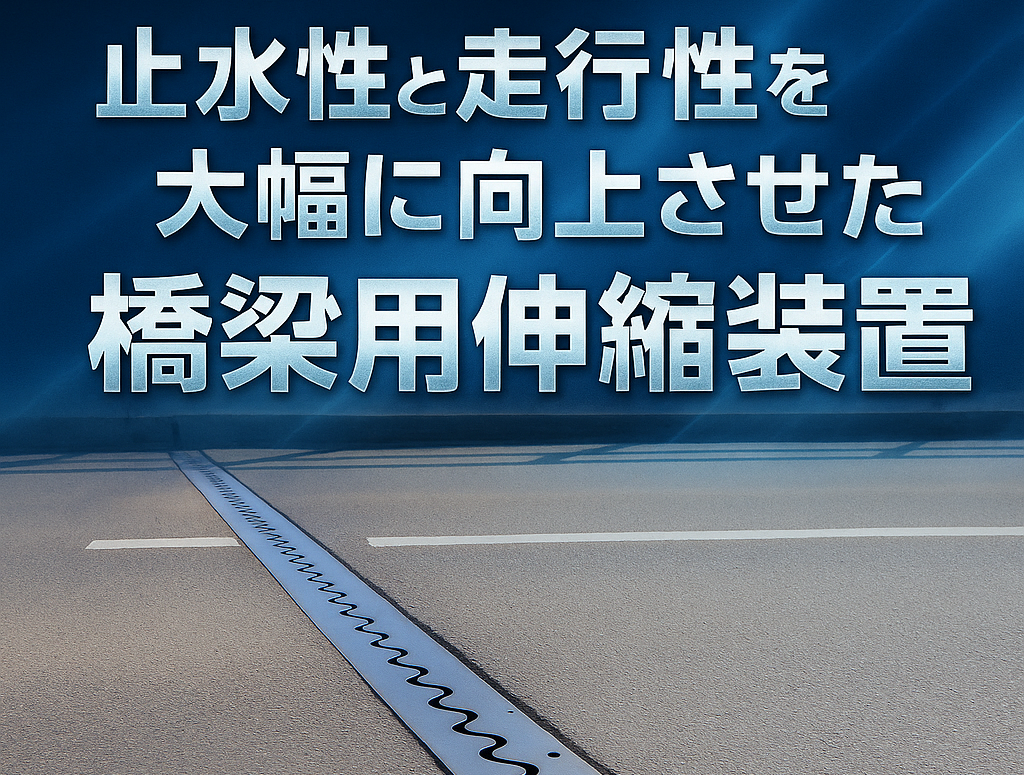COLUMN

トラス橋の特徴とは?メリット・デメリットを詳しく解説
トラス橋(きょう)は、“橋桁を「トラス構造」で補強した橋”です。主構造に弓なりの部材(アーチリブ)を用いたアーチ橋とともに、日本各地で見られます。
そのようなトラス橋には、他の構造形式の橋にはない強みがあることをご存知でしょうか。この記事では、トラス橋に見られる特徴や、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
まとめ
- ・トラス橋は三角形の集合体構造のため変形しにくく、トラス構造の種類により適した材料が選定される
- ・トラス橋の強みやメリットとして、デザイン性や強度も高いことなどが挙げられ、国の重要文化財にも指定されている
- ・トラス橋のデメリットは、点検する部材が多くメンテナンスが大変になり、建設費用も高くなりがちな点などにある
トラス橋の特徴とは?構造や材料について解説

トラス橋とは、三角形の集合体である「トラス構造」を主構造とした橋です。トラスの組み方によって、ハウトラスやプラットトラス、ワーレントラスなどの種類があります。
ここでは、トラス橋の特徴を3つ紹介します。
・橋桁を「トラス構造」で補強している
・三角形の集合体のため、変形しにくい
・材料に木材や鋼材を用いることが多い
橋桁を「トラス構造」で補強している
トラス橋の特徴は、橋の荷重を支える橋桁をトラス構造によって補強している点です。
トラス構造とは、主構(しゅこう)トラスとも呼ばれ、弦材や斜材、垂直材などの棒状の部材を三角形に組み合わせた構造を指します。
| トラスを構成する部材 | 各部材の特徴 |
|---|---|
| 弦材 | トラスの上下に配置される部材で、上弦材と下弦材がある |
| 斜材 | 弦材を斜めにつなぎ、骨組みを形成する部材を指す |
| 垂直材 | 弦材に対し垂直に配置された部材を指す |
各部材が交わる節点のことを、橋梁工学では格点(かくてん)と言います。古くは格点で部材を結合するため、ピンやヒンジを用いていました。しかし、ピン(ヒンジ)の箇所が強度上の弱点になり得ることから、近年では採用されていません。
現在は格点の弦材側で溶接するか、ガセット(当て板、繋ぎ板)と呼ばれる鋼板で連結することが一般的です。ガセットは、部材同士をリベット(小さな金属円板)で接合する際に、接合部の強度を高めたり、複雑な形状の接合を可能にしたりするために使用される板状の部材です。
三角形の集合体のため、変形しにくい
トラス橋に採用されるトラス構造は、三角形の集合体であるため、変形しにくいという特徴を持っています。
シンプルな構造の桁橋の場合、上から荷重がかかると橋桁がたわんだり、曲がったりする力が働きます。この力を曲げモーメントと言います。
トラス橋では、変形に強い三角形が骨組みになっているため、曲げモーメントが発生しません。力学上、トラスを形成する部材には、軸力(圧縮力・引張力)のみが作用します。そのため、圧縮力や引張力に強い部材を採用することで、桁橋と比べ高い強度を得られるのです。ただし、ハウトラスやプラットトラス、ワーレントラスなど、トラス構造の種類によって各部材に働く力が異なります。
| トラス構造の種類 | 部材に働く力 |
|---|---|
| ハウトラス | 斜材に圧縮力、垂直材に引張力が働く |
| プラットトラス | 斜材に引張力、垂直材に圧縮力が働く |
| ワーレントラス | 斜材に圧縮力・引張力が交互に働く |
例えば、斜材がハの字に並ぶハウトラスは、斜材に圧縮力、垂直材に引張力が働きます。一方、斜材が逆ハの字に配置されたプラットトラスでは、斜材に引張力、垂直材に圧縮力が働くのが特徴です。
逆W形のワーレントラスの場合、斜材の向きがパネル(格点間)ごとに変わります。そのため、斜材には圧縮力・引張力が交互に働きます。このような特徴から、ワーレントラスでは垂直材を省いた設計が可能です。
材料に木材や鋼材を用いることが多い
トラス橋には、主に木材や鋼材などの材料が用いられます。ハウトラスの場合、斜材に圧縮力が働くため、圧縮力に強いPC鋼材(注)を用いられやすいです。PC鋼材を用いたトラス橋は、通称「PC橋」と呼ばれます。古くは木造のハウトラスも盛んに建設されました。
注:PCは、プレストレスト・コンクリート(Prestressed Concrete)の略称で、鋼材をピンと引っ張って緊張させ、コンクリートを流し入れた材料を指します。コンクリートが固まってから鋼材を引っ張る方法もあります。
一方のプラットトラスでは、斜材に引張力が働き、かつ部材長も弦材や垂直材より長くなることから、引張強度が高い鋼材が用いられます。コンクリートは通常、圧縮強度に比べ引張強度が小さいことから、プラットトラスの建設にはほとんど採用されません。
トラス構造の種類に合わせ、圧縮強度や引張強度の高い材料を適材適所で用いることで、橋の強度を高められます。
トラス橋の3つのメリット
ここでは、トラス橋の3つのメリットを紹介します。
・桁橋と比べ、橋の最大支間長を長くできる
・強度が高いため、鉄道橋の建設に適している
・デザイン性も高く、国の重要文化財にも指定されている
桁橋と比べ、橋の最大支間長を長くできる

トラス橋の1つ目のメリットは、最大支間長の長い橋を建設できるという点です。
支間長とは、橋台や橋脚などの支点間の長さを指します。トラス橋は構造的に安定しており、軽量の部材で高い強度の橋を建設できるため、桁橋よりも支間長を長くすることが可能です。ケーブルで橋を吊り上げる斜張橋(しゃちょうきょう)と並び、長大橋の建設に適しています。
日本最大の支間長を誇るトラス橋は、上記画像の大阪のランドマークである港大橋(中央部の支間長510メートル)です。東京湾に架かる東京ゲートブリッジは、第2位となっています。
強度が高いため、鉄道橋の建設に適している
トラス橋の2つ目のメリットは、鉄道橋の建設に適しているという点です。
前述のとおり、トラス構造は変形に強く、曲げモーメントが発生しません。桁橋やラーメン橋(注)と比べ、重量物を支えられる丈夫な構造になっています。
注:ラーメン橋とは、柱と梁や、桁と橋脚を剛結し、一体化した「ラーメン構造」の橋を指します。
そのため、列車が通る鉄道橋として、古くからトラス橋が建設されてきました。例えば、日本初の複線用鉄橋である六郷川鉄橋(ろくごうがわてっきょう)も、橋長30メートルの鉄製トラス橋です。
明治時代に日本で鉄道が開業した当時、鉄道橋は全て木製でした。英国人の土木技師、リチャード・ボイルの設計により六郷川鉄橋が建設されると、以後は日本各地でトラス橋の建設が進みます。
明治7年(1874年)に大阪~神戸間で開通し、後に道路橋に改修された浜中津橋(はまなかつばし)もその一例です。
デザイン性も高く、国の重要文化財にも指定されている

トラス橋の3つ目のメリットは、強度だけでなく、景観性・デザイン性の高さを兼ね備えているという点です。特にワーレントラスは、構造上垂直材を必要としないため、すっきりとした見た目をしています。
またトラス橋は、さまざまな長さの部材を三角形に組み合わせることで、アーチ橋のような曲線を描く設計が可能です。例えば、曲弦プラットトラスや曲弦ワーレントラスは、上部が美しいアーチになっています。遠くから見ると、アーチ橋と見分けがつかないトラス橋も存在するほどです。
トラス橋には、文化的な価値や鉄道技術史における重要性を考慮し、国の重要文化財に指定されたものも数多くあります(以下、一例)。
| 名称 | 所在都道府県 | 構造形式 | 橋長 |
|---|---|---|---|
| 旧揖斐川橋梁 | 岐阜県 | 鉄製下路式ダブルワーレントラス桁橋 | 325.1メートル |
| 近鉄澱川橋梁 | 京都府 | 鉄製トラス橋 | 165メートル |
| 南河内橋 | 福岡県 | 鋼製二連トラス橋 | 133メートル |
| 古河橋 | 栃木県 | 鋼製単トラス桁橋 | 48.6メートル |
| 明治村六郷川鉄橋 | 愛知県 | 鉄製トラス橋 | 30メートル |
トラス橋の3つのデメリット
一方、トラス橋には3つのデメリットがあります。
・他の構造と比較すると、建設費用が高くなる可能性がある
・部材同士の組み合わせが必要なため、施工が複雑になる
・部材の点数が多いため、メンテナンスに手間がかかる
他の構造と比較すると、建設費用が高くなる可能性がある
他の構造形式の橋と比較すると、トラス橋は横方向に三角形を多数連結しており、複雑な構造です。上弦材や下弦材、斜材、垂直材など、部材の点数も多く、施工費用が高額になる可能性があります。
ただし、トラス橋は強度が高いため、橋の上部構造を軽量化できます。例えば、橋桁をより軽量な部材に置き換えるなどの工夫により、橋全体のコスト削減が可能となるでしょう。
部材同士の組み合わせが必要なため、施工が複雑になる
トラス橋には、施工に手間がかかるというデメリットもあります。
前述のとおり、トラス橋の主構造は、上下の弦材や斜材、垂直材などを組み合わせ、多数の格点で連結したものです。部材同士の組み合わせが必要なため、建設工事が複雑になり、時間や労力を要します。
またダブルワーレントラスのように、設計段階での応力計算が複雑になる構造(不静定構造)のトラス橋も存在します。ただし、通常のトラス構造の橋であれば、むしろ各部材に生じる軸力(圧縮力・引張力)は計算しやすく、手計算で容易に求めることが可能です。
部材の点数が多いため、メンテナンスに手間がかかる
トラス橋は部材の点数が多く、定期点検やメンテナンスに手間がかかるとされています。特に主構トラスは部材が入り組んでおり、死角となる箇所が多いため、目視での点検は容易ではありません。
しかし、近年は点検ロボットやドローン、全方位カメラなどの技術の導入が進んでおり、目視では確認しづらい箇所の点検も可能になっています。
トラス橋の特徴やメリット・デメリットについて知ろう
トラス橋はアーチ橋と並んで、日本で広く採用されている橋の構造形式です。
トラス橋は、変形に強い三角形の骨組み(トラス構造)でできており、軽くて丈夫という特徴があります。大阪市にある港大橋のように、中央部の支間長が500メートルを越える長大橋の建設も可能です。また強度だけでなく景観性にも優れており、岐阜県の旧揖斐川橋梁や、福岡県の南河内橋、栃木県の古河橋などが国の重要文化財に指定されています。
このようにメリットが多いトラス橋ですが、デメリットも存在します。例えば、設計・施工の複雑さやメンテナンスの難しさなどが、トラス橋のデメリットです。日本各地で見られるトラス橋の特徴や、メリット・デメリットについて知っておきましょう。